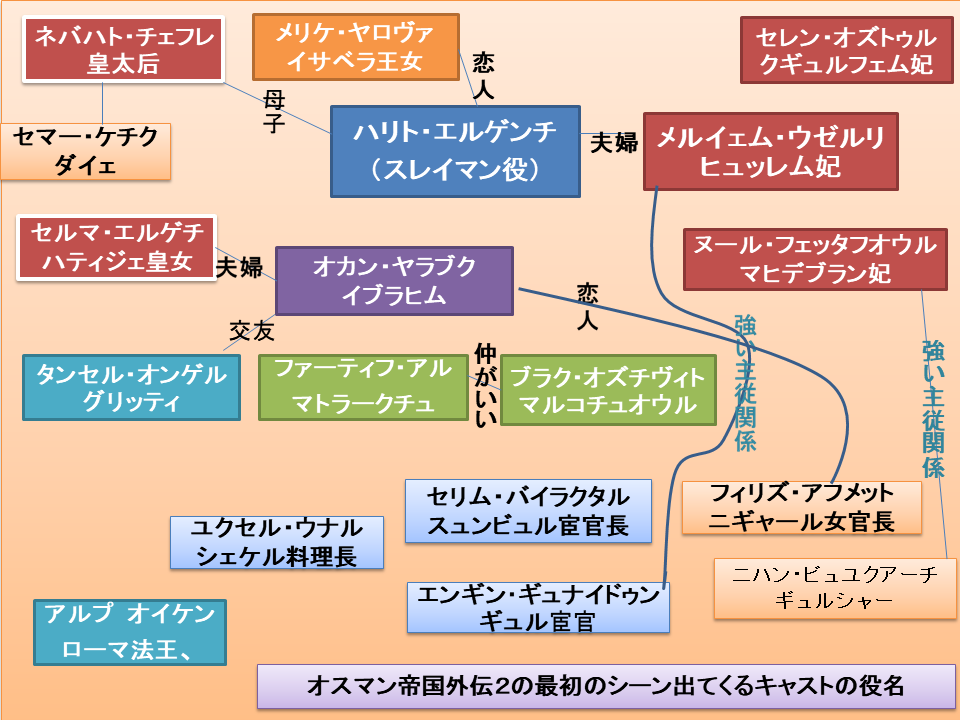BS日テレ

・ページ内の見だしリスト• 3 (14~16世紀)• 4 (17~18世紀)• 5 (19世紀)• 6 (20世紀)• 7 1922 参考 オスマン・トルコとは言わない 1990年代まで、日本ではこの国家はオスマン=トルコと言われ、教科書でもそう教えられていた。 セルジューク=トルコに対するオスマン=トルコ、というふうに覚えていた人も多いと思う。 しかし現在はお目にかからなくなり、専ら「オスマン帝国」とされている。 オスマン=トルコと言われなくなった理由は、まず彼らがそう自称したことはないこと、またトルコ人の国家と言うには無理があり、特にバルカン半島に進出してからは多民族国家となってトルコ人が多数派だったわけではないことが認識されたためである。 しかし「オスマン」という呼び方も実はようやく1876年制定の憲法に「オスマン国(デヴレティ・オスマニエ)」と明記されてからのことで、それ以前は公文書では「至高の国家(デヴレティ・アリイエ)」などと書かれていた。 それはオスマン王家のことを指すので、歴史的には「オスマン朝」とするのが妥当であろう。 しかし、長い歴史の中で単なる王朝の延長ではない国家機構を持つようになる。 以上のことから現在では研究者の中では「オスマン帝国」が定着している。 もっとも「帝国」にふさわしい国家になるのは1453年のメフメト2世の頃からであり、それ以前は「オスマン侯国」というのがふさわしい。 しかし600年続いたこの国家を一言で言えば便宜的ではあるが「オスマン帝国」という呼称に落ち着く。 <小笠原弘幸『オスマン帝国』2018 中公新書 p. 2-7> (1)オスマン帝国の概要 初期のオスマン国家 13世紀の西部は、の地方政権が支配していたが、の侵攻を受けて衰退、さらに東方からのモンゴルの侵入を受け、1242年その属国となった。 ルーム=セルジューク朝の弱体化に伴い、小アジアにはのイスラーム戦士の集団である ガーズィーが無数に生まれ、互いに抗争するようになった。 その中で有力なものが ベイ(君侯)を称し小規模な君侯国を創っていった。 オスマン帝国の創始者もそのようなベイの一人であり、、オスマンはガーズィを率いて小国家を独立させた。 またその西の領を個々に浸食していった。 第二代のオルハン=ベイはビザンツ領のを奪い、1326年に最初の首都とした。 小アジアの他の小さな君侯国を併合しながら、領土を拡大し、その間、イスラム法学者(ウラマー)を招いて国家の機構を整えていった。 バルカン半島に進出 小アジアの西北に起こった小勢力のオスマン国家であったが、14世紀にビザンツ帝国の分裂に乗じる形でダーダネルス海峡からに進出して勢力を拡大した。 ごろにはがを攻略、1366年に新首都エディルネと改称した。 さらに北上して、、など現地勢力を下しながら侵攻し、はので、は、でそれぞれキリスト教国連合軍を破り、いよいよを包囲する形勢となった。 ティムールに破れた後に再興 しかし、そのころ東方からが小アジアに侵入してきたため、バヤジット1世は軍を東にむけ、にでティムールと戦ったが敗れてしまった。 このためオスマン帝国は一時衰え、ビザンツ帝国は滅亡を免れた。 ティムール帝国は次ぎに矛先を東の(の時期)に向けたため、オスマン帝国は息を吹き返しはなどの軍隊の組織的な力を復活させて勢力を盛り返し、についにを攻略して、を都とする大帝国となった。 スルタンとカリフ オスマン帝国は、1396年のでキリスト教軍に勝ったがカイロに亡命していたアッバース朝のカリフの一族から、世俗的権力者としての称号を贈られてから、イスラーム教を保護する宗教国家として西アジアに大きな勢力を持つようになったとされている。 ただし、実際にはバヤジットの父のがすでにスルターンの称号を用いている。 さらににマムルーク朝を倒してからはスルタンは宗教的権威者としてカリフの地位を継承したと言われていたが、実際にが成立したのは後の18世紀である。 全盛期(16世紀)から停滞・衰退へ 領土拡張と世界史的影響 最盛期の16世紀には、西アジアから東ヨーロッパ、北アフリカの 三大陸に及ぶ広大な国土を支配した。 特にの時代、には(第1次)し、ヨーロッパキリスト教世界に大きな脅威を与え、・・の世界史的背景となった。 停滞と衰退 17世紀からは大帝国の維持に苦慮するようになり、北方のロシア・オーストリア、西方のイギリス・フランス・イタリアの勢力がおよんでくるようになり、同時に帝国内の非トルコ民族のアラブ民族などの民族的自覚()が芽生え、衰退期にはいる。 にはに失敗、オーストリア軍などの反撃を受け、にはでハンガリーを放棄し、バルカン半島で大きく後退した。 18世紀にはが総督が実質的に分離独立するなど、国力は急速に衰えるとともにオスマン帝国領を巡る列強の対立も激しくなった()。 18世紀ごろには、スルタンはの地位を兼ねるを明確にして、その権威を維持しようとした。 危機と改革 産業革命と市民革命を経たヨーロッパ列強は、19世紀に入ると明確な意図でオスマン領内の民族運動に介入し、侵略を本格化させたため、オスマン帝国は次々と領土を奪われていった。 からの、から2次にわたるがまさにその表れであり、オスマン帝国の苦悩は深くなった。 ようやく帝国内部にも改革の動きが生じ、によるのという上からの改革も試みられ、のではロシアの南下は一時とどめられた。 にはがアジア最初の憲法であるが制定されたが、翌年が勃発したことで憲法は停止になってしまった。 近代化への苦悩と滅亡 (1877~8)でロシアに敗れで大幅に国土を割かれたが、ロシアの南下を恐れるイギリス・オーストリアが介入、が開催され、で息を吹き返したが、は専制的な姿勢を強め、オスマン帝国はヨーロッパ列強から「瀕死の病人」といわれるようになった。 専制政治の打破を目指すが決起し、にがおこり、立憲国家となったが、新政権はして敗れ、敗戦の混乱の中でがによって遂行され、にオスマン帝国の滅亡()となった。 オスマン帝国の周辺 は、して、ヨーロッパ世界とアジア世界にまたがるイスラーム国家として強大化した。 この時から都はとなる。 15世紀後半のオスマン帝国の拡大によっての主導権を奪われた北イタリア商人はムスリム商人を介さず直接アジアとの取引をめざし、インド航路や西廻り航路の開拓を始め、それがヨーロッパ勢力のを出現される前提となった。 またビザンツ帝国滅亡に伴い、ギリシア人学者の多くはイタリアに亡命し、に刺激を与えた。 またオスマン帝国が全盛期となった16世紀の(大帝)の時代はヨーロッパでは宗教改革が進展し、同時に体制の形成が進んでいた時代であった。 そしてイランにはが成立、南アジア世界ではが登場し、東アジア世界では(の時期)の繁栄が続いていた。 15世紀末にはじまった大航海時代は、ヨーロッパ勢力のアジア進出がはじまった時期であるが、アジアにおいては、オスマン帝国・サファヴィー朝・ムガル帝国・明帝国(17世紀には清帝国に代わる)という巨大な専制国家が並立していたが、いまだ西欧世界に対して優位に立っていたと言える。 イスラーム教国であること イスラーム帝国の統治下では(シャリーア)が施行された。 しかし、従来のイスラーム国家と同じく、他の宗教に対しては租税を納めるかぎりにおいてその信仰を認めるという寛容策がとられた。 特にメフメト2世以降は、ギリシア正教・アルメニア教会・ユダヤ教の産教団には自治が認められたという(制)。 19世紀以降の末期となると、オスマン帝国をイスラーム信仰を核とした宗教国家として存続させるというパン=イスラーム主義と、トルコ民族を中心とした世俗的な多民族国家として再生を図るというパン=オスマン主義とが国家路線をめぐって対立することとなる。 参考 スルタン=カリフ制 イスラーム帝国では、政治権力者であるオスマン家のが同時にイスラーム教世界の統治者であると認識されていた。 そのはじまりは、にを倒して聖地との保護権を得たことをもって、スルタンはの宗教的指導者としてを称するようになった、とされていた。 つまり、オスマン帝国の君主は単に帝国の権力者にとどまらずイスラーム世界の中心にあると意識されるていた。 これはといわれる体制であるが、最近の研究では、18世紀のオスマン帝国の衰退期に、帝国の権威を強めるために創作されたことで、歴史的事実では無いことが明らかにされた。 激しい征服活動 を中核とした強力な軍事力のもと積極的な征服活動を展開してし、さらにて、その後も数度にわたってウィーンを包囲するなど、隣接するキリスト教カトリック世界に対して大きな脅威を与えた。 一方、東側で隣接するシーア派イスラーム教のイランとも激しく抗争した。 オスマン帝国の征服活動を支えた軍事力は、初期においてはという知行地を与えられたトルコ人の騎士であるであったが、次第に独自の常備軍制度であるといわれる軍団が中心となっていく。 多民族国家と「柔らかい専制」 オスマン帝国はによる征服王朝であり、支配層はトルコ人であったが、その領内にはアラブ人、エジプト人、ギリシア人、スラヴ人、ユダヤ人などなど、多数の民族を含む、複合的な多民族国家であった。 その広大な領土と多くの民族を統治するため、中央集権的な統治制度を作り上げたが、その支配下の民族に対しては、それぞれの宗教の信仰を認め、イスラーム教以外の宗教であるキリスト教ギリシア正教やユダヤ教、アルメニア教会派など 非ムスリムにたいして改宗を強制せず、宗教的集団を基本的な統治の単位としていた(これをという)。 このような、中央集権的な専制国家でありながら、支配下の民族に対して宗教的にも政治的にも一定の自治を認めていたオスマン帝国の特徴は 「柔らかい専制」と言われてる。 <鈴木董『オスマン帝国 -イスラム世界の柔らかい専制-』1992 講談社現代新書> 中央集権体制 オスマン帝国はスルタンといえどもイスラーム法の規制を受ける宗教国家であり、また「柔らかい専制」と言われる他宗派、他民族への寛容な性格を持っていたが、同時に専制国家としての中央集権体制の維持、強化に努めていた。 スルタンの直轄地は州・県・郡に分け、州には総督、県には知事、郡にはイスラーム法官を中央から派遣した。 直轄地以外にはやのように現地有力者を 太守(パシャ)に任命して統治させた。 また黒海北岸のなどのように属国として支配した地域もある。 スルタンを補佐し、実質的な政治にあたる官僚機構の頂点にいたのが大宰相()であり、形式的にはスルタンの御前会議で最高政策が決定された。 官僚(書記を意味するキャーティプといわれた)は文書の管理にあたり、宮廷と国家の財政を実質的に処理した。 補足 オスマン帝国には公用語がなかった 「公用語のない国家があると聞けば、そんなものは、お伽噺の世界にしかあり得ないと誰しもが思うことだろう。 しかしそういう国が、少なくとも一つだけは、近代の世界に存在したのである。 ・・・オスマン・トルコ帝国には、はじめのころ、公用語と呼ぶべきものがまったくなかった。 ・・・オスマン・トルコ帝国の場合、特定の言語を被支配者に押しつけようという意図が、帝国崩壊にいたるまでついぞなかったのである。 」イスラーム教徒にとってはアラブ語が、キリスト教徒はそれぞれギリシア語、アルメニア語、アッシリア語を宗教用語として用いていた。 一方、文化教養言語としてはペルシア語が幅をきかせ、商業用語としてはギリシア語を用いるのが普通だった。 ずっとあとになってスルタンの宮廷で成立したオスマン語(オスマンル)は、トルコ語を基礎にアラブ語とペルシア語の語彙と文法構造を織り交ぜた混成語であった。 公文書はオスマン語で書かれることになっても、宮廷外で一般民衆に強制されることはなかった。 トルコ語は支配民族の言語であったにもかかわらず、「無学文盲の輩」の言葉として蔑まれ、近隣のペルシア語、アラブ語、ギリシア語からおびただしい数の語彙を借用した。 帝国末期にギリシア人、ブルガリア人、ルーマニア人、セルビア人、アルバニア人などが次々と民族国家を形成していく過程で、その反動として初めてトルコ人にも民族意識が芽生える。 トルコ語が書記言語として成立したのはトルコ共和国が成立した後に、アラブ文字を用いるオスマン語にかわってラテン文字を採用してトルコ語が真の意味でトルコの公用語となった。 <小島剛一『トルコのもう一つの顔』1991 中公新書 p. 22-24> の建国から数えれば600年以上、を都としてからでも約470年存続し、に消滅した。 14~20世紀初頭まで西アジアからバルカン半島を支配したイスラーム教国オスマン帝国のまとめその推移を世紀ごとにまとめると次のようになる。 14世紀 バルカン半島への進出 オスマン帝国第2代オルハンはビザンツ帝国のヨハネス6世の娘を妻とし、その内紛に乗じてに軍団を進め、1354年に獲得したのガリポリ(トルコ語ではゲリボル)を拠点に、バルカン内部に進出し、コンスタンティノープルのビザンツ帝国を包囲する形勢となった。 ごろには第3代のはを攻略、1366年にはそこに新しい都エディルネを建設した。 その間、異教徒の奴隷軍団を育成、後ののもとを創った。 コソヴォとニコポリス オスマン帝国の進出に脅威を感じたセルビアやルーマニア、ブルガリアなどのキリスト教国のバルカン諸国連合軍は、ので迎え撃ったが、のオスマン帝国軍の前に敗れ去った。 次いでハンガリー王がヨーロッパのキリスト教国に呼びかけて十字軍を組織し、、オスマン勢力圏に南下したが、はそれを迎え撃ち、で撃破してた。 こうして惜しまん勢力圏はドナウ川流域まで及び、バヤジット1世はいよいよ標的をコンスタンティノープルに定めた。 ティムールとの戦いのため後退 いよいよバヤジットの率いるオスマン軍が迫り、コンスタンティノープルは危機を迎えたが、そのとき、中央アジアを制圧したティムール帝国が小アジアまで迫ってきたため、バヤジットはコンスタンティノープル攻撃を中止し、西進してと戦うこととなった。 このため、コンスタンティノープルの陥落は約50年遅れることとなったといわれる。 バヤジットとティムールの決戦は、として展開されたが、バヤジットは敗れ、捕虜となったためオスマン帝国は事実上、活動を停止せざるを得なくなった。 15世紀 バルカン半島の制圧 ほぼ50年後、国力を回復したは、などの軍事力を高度に組織してコンスタンティノープル攻略を再開、ついにに占領し、た。 コンスタンティノープルはとしてオスマン帝国の都となり、イスラーム文化が扶植され、一変した。 さらにメフメト2世はバルカン半島のほぼ全域を征服し、カフカス地方や北海北岸にも領土を拡大した。 オスマン帝国によって東方キリスト教世界が征服されたことは、西ヨーロッパのキリスト教世界に大きな衝撃と影響を与え、ビザンツ帝国の滅亡の前後に、多くのギリシア人の学者はイタリアのに亡命したが、それによってイタリアのに刺激を与えた。 16世紀 オスマン帝国の全盛期 はにイランから侵攻してきた軍をで撃破し、領土を東方に拡大した。 さらににはエジプトのを倒して聖地との保護権を得たとされる。 次いでの時にスルタンの専制支配は全盛期となり、、で軍を破り、さらにので宗教改革期のヨーロッパにとって大きな脅威を与えた。 この遠征は長期化を避けて撤退したので失敗に終わったが、一方でスレイマン1世は地中海方面への進出を積極化し、1522年はを征服して、をクレタに追い出した。 にはの勝利で神聖ローマ帝国・ローマ教皇・ヴェネツィアの連合艦隊を破って地中海の制海権を得た。 一方、東方ではと戦い領土を広げた。 1534年にイラクを征服してペルシア湾からインド洋への関心を深めた。 インド洋にはすでにポルトガルが進出し、1509年のでマムルーク海軍を破り、西インドのグジャラートのディウに拠点を設けていた。 1538年にオスマン海軍はポルトガルの拠点ディウを攻撃したが、これは成功しなかった。 フランス王フランソワ1世との関係 また、スレイマン1世は、ヨーロッパ諸国の国際関係と深く関わり、神聖ローマ帝国のと対立していたフランスのと結び、フランス商人の帝国内での居住などの通商特権を認めた。 これは後にオスマン帝国のスルタンが恩恵として外国に貿易特権を与えるの原型となったものであり、オスマン帝国のヨーロッパ諸国への従属の第一歩ともされている。 かつてはカピチュレーションはスレイマン1世の時に定められたとされていたが、現在の研究ではそれが法制化されたのは次のセリム2世の時であっととが判明している。 レパントの海戦の敗北はオスマン帝国の衰退を意味しない スレイマン大帝の時にエーゲ海の出入り口をオスマン海軍が押さえたのに続き、その死後、セリム2世はを占領し、東地中海を制圧した。 これはヨーロッパ諸国にとっての危機であったので、スペインのフェリペ2世はヴェネツィアとローマ教皇に働きかけて連合艦隊を編成し、ので激突した。 このときはスペインの無敵艦隊の活躍でオスマン海軍は敗れ、地中海の制海権拡張はいったん後退した。 しかし、間もなくオスマン海軍は再建され、1574年にはを征服してを滅ぼし、アルジェリアに支配を及ぼした。 このようにオスマン海軍はレパントの海戦で敗れているが、まもなく地中海制海権を回復しており、衰退に一気につながったような印象を持つとそれは間違いである。 西洋中心の世界史の陥りやすい錯覚なので注意すること。 17世紀 衰退期 17世紀になると、は次第に政治の実権から離れ、宮廷出身の軍人が、大宰相(、スルタンの絶対的代理人とされた)として政治の実権を握るようになった。 1622年、スルタンのオスマン2世はの改革をはかり、逆に反乱が起きて暗殺されてしまった。 またスルタンの後宮(ハーレム)が政治に絡むなど、混迷が続く。 バルカン半島でのハプスブルク家神聖ローマ帝国()が(1618~48年)で混乱し、オスマン帝国の進出の好機であったが、その動きはなく、東方の朝は全盛期を迎え、にはを占領するなどオスマン帝国にとっての敵対勢力となりつつあった。 アッバース1世の死後、オスマン帝国は1638年にバグダードを奪回した。 第2次ウィーン包囲の失敗 、スルタンに代わって実権を握った大宰相カラ=ムスタファは、かつてスレイマン大帝が成し遂げられなかったの都ウィーン征服を実現しようと、を実行した。 これはフランスのの了解の上での軍事行動であったが、神聖ローマ皇帝レオポルト1世は一旦ウィーンを脱出し、バイエルン、ザクセン、などドイツ諸侯、さらになどに来援を要請して態勢を整え、その結果オスマン帝国軍はウィーンを落とすことはできず、撤退した。 第2次ウィーン包囲が失敗に終わったことはオスマン帝国のヨーロッパ領土の喪失の始まりとなった。 カルロヴィッツ条約まで 第2次ウィーン包囲に失敗したオスマン帝国軍はバルカン半島を南下、それを追う神聖ローマ皇帝レオポルト1世(オーストリア皇帝)は、ローマ教皇の仲介で、ポーランドやヴェネツィア共和国、ロシアなどと神聖同盟を結成、十字軍の再来という形でオスマン帝国領に侵攻した。 オスマン軍はオーストリア軍を指揮した将軍オイゲン公に激しく追撃され、1686年にはブダペストを奪われた。 ヴェネツィア軍はアテネのオスマン軍を攻撃、このときパルテノン宮殿が爆破された。 後退を続けたオスマン帝国は、、を神聖同盟側と締結し、ハンガリーを放棄した。 ハンガリーがオーストリアに奪還されたことは、オスマン帝国の後退を象徴する出来事となった。 しかし、隣接するドイツ、オーストリアの進出、によってを失うなど、オスマン帝国の領土は蚕食されるようになった。 さらに支配下のアラブ人の独立運動が始まり、アラビアで始まったイスラーム改革運動であるが、独自の国家を樹立するまでになった。 オスマン帝国の内部は、古いの勢力が残存し、またと言われる地方の有力者が徴税請負権をもって富を蓄積し、分権化が進み、改革の必要が認識されるようになった。 19世紀 改革と停滞 フランス革命勃発と同じ時期に即位したがまず改革に着手し、ついでのによるという思い切った手が打たれた。 一方、ナポレオンのを機にではエジプト総督の政権が成立するなど、が続いた。 ギリシアの独立 さらにからがおこり、ヨーロッパ列国がオスマン帝国領内の民族独立運動に介入してといわれる列強の対立が表面化した。 、でオスマン海軍は英仏露の連合艦隊に敗れ、近代化の遅れが露呈した。 1829年、オスマン帝国はロシアとの アドリアノープル条約で黒海北岸を割譲し、のでギリシアの独立を認めた。 この結果、オスマン帝国の権威は大きく低下した。 エジプト・トルコ戦争 このような情勢のもと、エジプトのムハンマド=アリーはオスマン帝国に戦いを挑み、から2次にわたるとなる。 この戦争では一時シリアを失ったが、列強が介入してムハンマド=アリーはシリアから退き、エジプト=スーダンの総督の地位の世襲を認められるにとどまった。 また、ムハンマド=アリーのエジプトが台頭することはイギリスのインド支配に障害になるところから、イギリスは1838年にを締結して、エジプトの貿易も抑えようとした。 タンジマート こうしてオスマン帝国の領土はトルコ人の居住地区だけに縮小されていった。 そのような危機に面して、オスマン帝国の中では、によるに始まるなどの近代化が模索されはじめた。 クリミア戦争 オスマン帝国の弱体化に乗じてロシアが南下政策を強めると、フランスのナポレオン3世が介入、またイギリスもロシアの東地中海方面への進出によってインドへのルートが脅かされるので、オスマン帝国を支援し、、イギリス・フランス・オスマン帝国の連合軍とロシア軍のとなった。 この戦争ではイギリス・フランス軍がロシア軍を破り、その南下は一時、食い止められることとなった。 ミドハト憲法 にはの即位とともにアジア最初の憲法であるが制定されたが、にロシアが南下を再開してが勃発すると憲法は停止され、改革は頓挫してスルタン専制政治に復帰した。 露土戦争とベルリン条約 クリミア戦争で一旦後退したロシアは、が農奴解放などの上からの近代化を図り、国力を回復した上で、1870年代に再び南下政策を強めた。 、ロシアはスラヴ系民族キリスト教徒(ギリシア正教)の保護を口実にトルコに宣戦布告となった。 これが露土戦争であったが、装備に劣るオスマン帝国は各地で敗れ、ロシア軍がコンスタンティノープルに迫る中、3月イスタンブル近郊で講和会議を開き、が締結された。 オスマン帝国が大きく譲歩し、ロシアがバルカンへの進出を果たしたが、それに対して、オーストリア=ハンガリー帝国とイギリスが強く反発し、ロシアとの間に戦争となる危機が生じた。 そこで、ドイツ帝国のが調停に乗り出してが開催され、その結果のにが締結された。 これは、ビスマルクの構想によってオスマン帝国を犠牲にしてヨーロッパ列強の不満を解消し平和を実現するというものであった。 その要点は次のようなものである。 オスマン帝国領であった、、の三国は独立する。 はオスマン帝国を宗主国とする自治国にとどまるが、領土を3分の1に縮小される。 オスマン帝国領であったはオーストリアの行政権(統治権)が認められる。 同じくオスマン帝国領であった島の行政権(統治権)はイギリスに認められる。 瀕死の病人 露土戦争の敗北と、ベルリン条約締結の結果、オスマン帝国は大幅に領土を縮小させ、その弱体をさらしたことになり、西欧列強から 「瀕死の病人」(またはヨーロッパの病人)と見なされるようになった。 対外的な失点が続いただけでなく、19世紀前半のエジプト=トルコ戦争以来、オスマン帝国はタンジマートという上からの改革を進めてきたが、スルタンを頂点とした政治や官僚制の腐敗(官職の売買や同族登用=ネポティズム)がはびこり、国力は次第に衰退しており、「瀕死の病人」の病巣は内部にあった。 青年トルコ革命と領土の縮小 19世紀後半から続くの専制政治に対して、に(統一と進歩委員会)によるが起こってアブデュルハミト2世は退位し立憲君主政となった(スルタンは有名無実化したが形式的にはまだ存在した)。 この革命の混乱に乗じて、はを強行し、またそれまでオスマン帝国内の自治国であったが完全独立を宣言した。 1911年にはイタリアがオスマン帝国領のトリポリ・キレナイカに侵攻してがおこり、セルビア・ブルガリア・ギリシアなどバルカンの諸国は1912年にを結成してオスマン帝国領に侵攻し、と周辺諸国による侵略が続いて、オスマン帝国は領土を次々と失った。 青年トルコ政権と第一次世界大戦参戦 このような情況の中で、1914年、ら青年トルコはスルタンから実質的権限を奪うクーデターを敢行し、を樹立、立憲君主政・議会制を形骸化させて軍部独裁政権とした。 1914年、が勃発すると、この青年トルコ政権は反ロシア、反スラム民族の立場から、ドイツ・オーストリアの同盟国側に付いて11月12日にした。 それに対してイギリスは、12月19日、実質的に支配下に置いていたを完全な保護国とすることをオスマン帝国に通知した。 エジプトを完全にオスマン帝国から分離し、を確保するのがねらいであった。 翌15年2月、2万のオスマン帝国軍はスエズ運河の奪還を目指して進軍し、その一部は運河を越えたが、結局イギリス軍に撃退され、作戦は失敗した。 第一次世界大戦の敗北と危機 ダーダネルス海峡進出を狙うイギリス・フランス軍とはで戦い、一軍人であったの活躍もあって防衛に成功するなど、健闘したが、次第に他の同盟国と同じように劣勢に陥った。 バルカンでは首都イスタンブルに連合軍が迫り、中東ではイギリス軍がエジプトからパレスティナに侵攻、アラブ人の反乱も拡大してオスマン軍は敗北を重ね、ついに1918年10月、スルタンのメフメト6世は密かに連合国と取引して自己の地位を保障されたかわりに、停戦に応じた。 青年トルコ政府は裏切られた形となりエンヴェル=パシャはドイツに亡命しは倒れた。 そのドイツも11月には降伏し、オスマン帝国を含む同盟国側は敗北した。 しかし、西アジアでイギリス軍に支援されたアラブ軍と戦っていたは降伏を拒否して抵抗を続けた。 翌1919年5月、イギリスの支援を受けたギリシア軍が(スミルナ)に侵攻し、が勃発、ムスタファ=ケマルはトルコ国民軍を組織してゲリラ戦で抵抗し、20年4月にはアンカラにを招集し、国民軍を組織して抵抗を続けた。 一方スルタン政府が1920年8月、連合国に強要されたを締結し、しイギリスとフランスのとすることを承認したことは、トルコ民族の激しい反発を呼び起こし、ムスタファ=ケマルの国民軍への期待が高まった。 トルコ国民軍は1921年8月、ギリシア軍を破って形勢を逆転させた。 トルコ革命と帝国の滅亡 、の指導する大国民議会は満場一致で(帝政廃止)を可決、メフメト6世はイギリス軍艦でマルタ島に亡命し、オスマン帝国は滅亡した。 1923年7月、改めて連合国とを締結してアナトリアの領土と主権の回復に成功、アンカラの大国民議会はを宣言し、を初代大統領に選出した。 これによって近代トルコ国家であるが成立し、同年、トルコ共和国は諸外国に認めていたも廃止した。 ムスタファ=ケマルは次々と内政改革を実行し、が進展することとなった。
次の