田辺聖子さんの解説|特集!木版源氏物語絵巻|桐壺
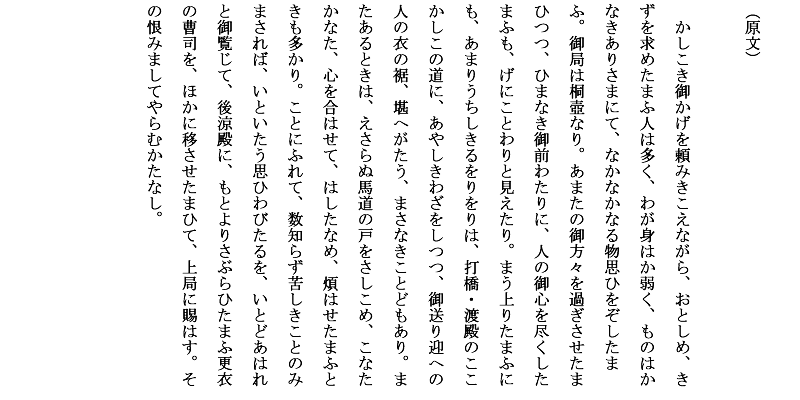
御時=御代、天皇の代、 に=断定の助動詞「なり」の連用形、接続は体言・連体形、「~である」 か=疑問の係助詞、結びは連体形となるはずだが、ここでは省略されている。 「ありけむ」が省略されていると考えられる。 場合によって敬語になったり、助動詞がついたりする。 「にや・にか」だと、「ある・侍る(「あり」の丁寧語)・あらむ・ありけむ」など 「にこそ」だと、「あれ・侍れ・あらめ・ありけめ」など いつの帝の御代であっただろうか、 女御 にょうご 、 更衣 こうい あまた 候ひ 給ひ けるなかに、 女御=天皇が囲っている女性、高位の女官、更衣よりも上 候ひ=ハ行四段動詞「候ふ(さぶらふ)」の連用形、謙譲語。 お仕え申し上げる、お仕えする。 動作の対象である天皇を敬っている。 作者からの敬意。 どの敬語も、その敬語を実質的に使った人間からの敬意である。 給ひ=補助動詞ハ行四段「給ふ」の連用形、尊敬語。 動作の主体である女御・更衣を敬っている。 作者からの敬意 ける=過去の助動詞「けり」の連体形、接続は連用形 女御や行為の方が、大勢お仕え申し上げていらっしゃった中に、 いと やんごとなき 際 きわ にはあら ぬが、 すぐれて 時めき 給ふあり けり。 動作の主体(寵愛を受けて栄えている人)である桐壷の更衣を敬っている。 作者からの敬意ちなみに、直後に「人」が省略されているため連体形となっている。 「~していらっしゃる 人」 けり=過去の助動詞「けり」の終止形、接続は連用形 それほど高貴な身分ではない人で、格別に帝のご寵愛を受けていらっしゃる方があった。 はじめより、我はと 思ひあがり 給へ る御方々、 思ひあがり=ラ行四段動詞「思ひあがる」の連用形、自負する、気位を高く持つ 給へ=補助動詞ハ行四段「給ふ」の已然形、尊敬語。 動作の主体である御方々(女御たち)を敬っている。 作者からの敬意 る=完了の助動詞「り」の連体形、接続はサ変なら未然形・四段なら已然形。 直前に四段の已然形があることから判断できる、直後に体言が来ていることから連体形だと考えて活用から判断してもよい。 最初から私こそは(帝のご寵愛を得る)と自負していらっしゃった女御の方々は、 めざましき ものに おとしめ そねみ 給ふ。 めざましき=シク活用の形容詞「めざまし」の連体形。 心外で気にくわない、あきれたものだ。 すばらしい、立派だ おとしめ=マ行下二段動詞「貶しむ(おとしむ)」の連用形、見下げる、さげすむ そねみ=マ行四段動詞「嫉む(そねむ)」の連用形、羨ましくて憎く思う、ねたむ 給ふ=補助動詞ハ行四段「給ふ」の終止形、尊敬語。 動作の主体である御方々(女御たち)を敬っている。 作者からの敬意 (格別のご寵愛を受けているこの更衣を)心外で気にくわない者として軽蔑したり嫉妬したりなさる。 同じ程、それより 下 げ 臈 ろう の更衣たちは、まして やすから ず。 下臈=名詞、身分の低い者 やすから=ク活用の形容詞「安し」の未然形、易しい、安らかである ず=打消の助動詞「ず」の終止形、接続は未然形 (この更衣と)同程度、あるいはそれより低い身分の更衣たちは、(女御たちよりも)いっそう心中穏やかでない。 朝夕の宮仕につけても、人の心をうごかし、恨みを負ふ 積もり に やあり けむ、 積り=名詞、積もること、見積もり に=断定の助動詞「なり」の連用形、接続は体言・連体形 や=疑問の係助詞、結び(文末)は連体形となる。 係り結び けむ=過去推量の助動詞「けむ」の連体形、接続は連用形、係助詞「や」を受けて連体形となっている。 係り結び。 朝夕の宮仕えにつけても、周りの人の心を動かしてばかりいて、恨みを受けるのが積み重なったのであったのだろうか、 いと あつしくなりゆき、 物心細げに 里がちなるを、 あつしく=シク活用の形容詞「篤し(あつし)」の連用形、病気が重い、危篤の状態だ 物心細げに=ナリ活用の形容動詞「物心細げなり」の連用形、なんとなく心細い、頼りなく不安である 里がちなる=ナリ活用の形容動詞「里がちなり」の連体形、実家に帰っていることの多い様子、直後に「こと」が省略されているため連体形になっている。 (この更衣は)ひどく病弱になってゆき、なんとなく心細そうな様子で実家に帰りがちであることを、 いよいよ 飽かず あはれなるものに 思 おぼ ほし て、 いよいよ=副詞、ますます、なおその上、とうとう 飽か=カ行四段動詞「飽く」の連用形、満足する、飽き飽きする あはれなる=ナリ活用の形容動詞「あはれなり」の連体形。 「あはれ」はもともと感動したときに口に出す感動詞であり、心が動かされるという意味を持つ。 しみじみと思う、しみじみとした情趣がある 思ほし=サ行四段動詞「思ほす(おぼほす)」の連用形、尊敬語。 お思いになる。 動作の主体である帝を敬っている。 作者からの敬意。 (帝は)ますます飽き足らず愛しい者とお思いになって、 人の そしりをも え 憚 はばか ら せ 給は ず、 そしり=名詞、そしること、非難 え=副詞、下に打消の表現を伴って「~できない」 憚ら=ラ行四段動詞「憚る(はばかる)」の未然形、障害があっていき悩む、進めないでいる せ=尊敬の助動詞「す」の連用形、接続は未然形。 「す・さす・しむ」は直後に尊敬語が来ていないときは「使役」だが、尊敬語が来ているときは文脈判断。 「給は」と合わせて二重敬語となっており、動作の主体である帝を敬っている。 作者からの敬意 給は=補助動詞ハ行四段「給ふ」の未然形、尊敬語。 ず=打消の助動詞「ず」の連用形、接続は未然形 人々の非難をも気にすることがおできにならず、 世の 例 ためし にもなり ぬ べき 御もてなし なり。 例=名詞、先例、話の種、手本 ぬ=強意の助動詞「ぬ」の終止形、接続は連用形。 「つ・ぬ」は「完了・強意」の二つの意味があるが、直後に推量系統の助動詞「む・べし・らむ・まし」などが来るときには「強意」の意味となる べき=推量の助動詞「べし」の連体形、接続は終止形(ラ変なら連体形)。 ㋜推量㋑意志㋕可能㋣当然㋱命令㋢適当のおよそ六つの意味がある。 御もてなし=名詞、ふるまい、とりはからい、待遇、 なり=断定の助動詞「なり」の終止形、接続は体言・連体形 世の話の種にもなってしまいそうなおふるまいである。 上達部 かんだちめ 、 上人 うえびと なども あいなく目を そばめ つつ、 上達部=公卿、大臣などで三位以上の人 上人=殿上人、上達部よりは位が低い あいなう=ク活用の形容詞「あいなし」の連用形が音便化したもの、わけもなく、なんとなく。 つまらない。 気に食わない。 上達部や殿上人たちもなんとなく目を背けるという状態で、 いと まばゆき 人の御おぼえ なり。 人の御おぼえ=人は「桐壷の更衣」のことで、御おぼえとは「帝のご寵愛を受けること」である、「桐壷の更衣へのご寵愛」 なり=断定の助動詞「なり」の終止形、接続は体言・連体形 本当にまぶしいほどのこの更衣へのご寵愛ぶりである。 もろこし にも、 かかる 事の起りに こそ世も乱れ 悪 あ しかり けれと、 もろこし=中国 かかる=連体詞、このような、こういう、ここでいう「このような」とは「人々の批判にも耳を傾けず、国の王が一女性への愛に溺れるといったこと」である 事の起こり=原因・契機、「事(名詞)/の(格助詞)/起こり(名詞)」 こそ=強調の係助詞、結び(文末)は已然形、ここでは「けれ」が結びとなっている。 悪しかり=形容詞「悪し(あし)」の連用形、シク活用、よくない、好ましくない。 けれ=過去の助動詞「けり」の已然形、接続は連用形。 係助詞「こそ」を受けて已然形となっている。 係り結び。 「中国においても、こういうことが原因となって、世の中も乱れ悪くなった。 」と、 やうやう 天 あめ の 下 した にも あぢきなう、人の もてなやみぐさに なりて、 やうやう(漸う)=副詞、だんだん、しだいに、かろうじて 天の下=名詞、この世の中、天下、世間 あぢきなう=ク活用形容詞「味気無し」の連用形が音便化したもの。 つまらない、苦々しい、情けない。 かいがない、無益だ、どうしようもない。 もてなやみぐさ(持て悩み草)=名詞、取扱いに困るもの、悩みの種 なり=ラ行四段動詞「成る」の連用形 しだいに世間でも苦々しく思われ、人々の心配の種になって、 楊 よう 貴 き 妃 ひ の 例 ためし も 引き出で つ べくなりゆく に、 例=名詞、先例、話の種、手本 引き出づ=ダ行下二段、引き出す つ=強意の助動詞「つ」の終止形、接続は連用形。 「つ・ぬ」は「完了・強意」の二つの意味があるが、直後に推量系統の助動詞「む・べし・らむ・まし」などが来るときには「強意」の意味となる。 べく=推量の助動詞「べし」の連用形、接続は終止形(ラ変なら連体形)。 ㋜推量㋑意志㋕可能㋣当然㋱命令㋢適当のおよそ六つの意味がある。 に=接続助詞、「を・に・ば・ば・ど・も・が」が使われた直後に主語が変わる可能性がある。 ここでは次の文から主語が桐壷の更衣に変っている。 楊貴妃の先例までも引き合いに出しそうなほどになっていくので、 いと はしたなきこと多かれ ど、 かたじけなき 御心ばへ の 類 たぐい なきを たのみにて 交 ま じ らひ 給ふ。 はしたなき=ク活用の形容詞「はしたなし」の連体形、迷惑だ、不都合だ。 中途半端だ。 きまりが悪い。 体裁が悪い。 ど=逆接の接続助詞、活用語の已然形につく。 かたじけなき=ク活用の形容詞「かたじけなし」の連体形、恐れ多い、もったいない。 恥ずかしい、面目ない 御心ばへ=心遣い、趣向 の=格助詞、用法は主格、訳「帝の心遣い が比類のないほどなのを」 類なし=形容詞ク活用、並ぶものがない たのみ=マ行四段動詞「頼む」の連用形。 ここだと「頼みに思わせる、あてにさせる」といった意味になる。 交じらひ=ハ行四段動詞「交じらふ」の連用形、まじる、仲間に入る、交際する、宮仕えする 給ふ=補助動詞ハ行四段、尊敬語、動作の主体である桐壷の更衣を敬っている (桐壷の更衣にとって)まことに不都合なことが多いけれども、(帝の)もったいないほどの御心遣いが比類もないほどなのを頼みに思って、(他の女御・更衣の方々と)宮仕えしていらっしゃる。 続きはこちら -.
次の