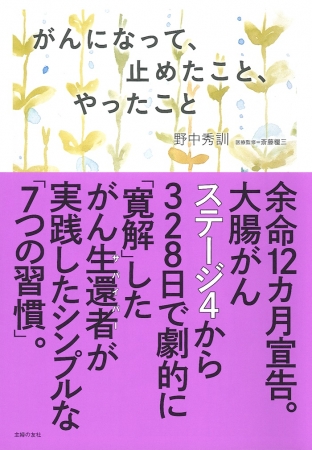膵臓癌ステージ4bの余命は1年以内が多い
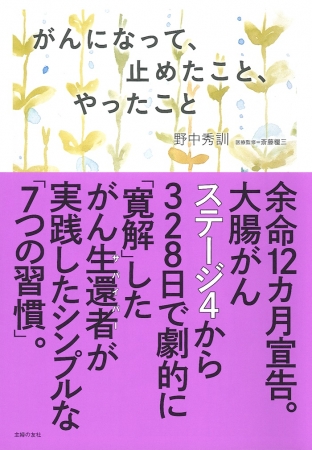
大腸がんの治療方針は各種検査から病気のひろがりを判断し、進行度(ステージ)を診断して決定します。 がんと診断されると「 私はあとどれだけ生きられるのだろう」と思われるかもしれません。 この平均余命はがんであってもどの部分のがんかによって異なりますし、 同じ大腸がんであってもがんの種類やステージによって異なります。 簡単に表現すると5年生存率はその病気になった人が5年後生きている確率です。 生存率が高い場合は治療効果が得られやすいがんと考えられます。 大腸がんの5年生存率はがんの中ではやや良い数字になっていますが、病気が発見されたときのステージが進んでいれば進んでいるほど5年生存率は下がるため、早期発見が重要です。 大腸がんの種類と進行度について 大腸がんの種類 大腸がんにはいくつかの分類があります。 部位による分類 大腸がんは病気のある部位によって大きく結腸と直腸に分けられ、さらに結腸は細かく分類されます。 結腸がん• 盲腸がん• 上行結腸がん• 横行結腸がん• 下行結腸がん• S状結腸がん 直腸がん 見た目による分類 がんの見た目による分類を肉眼的分類といいます。 肉眼的分類はまず早期がんと進行がんに大きく分けられ、さらにその形によって細かく分類されます。 早期がん <隆起型>• 有茎性(Ip型)• 亜有茎性(Isp型)• 無茎性(Is型) <表面型>• 1型(腫瘤型)• 2型(潰瘍限局型)• 3型(潰瘍浸潤型)• 4型(びまん浸潤型)• 5型(分類不能型) 細胞の種類による分類 病変を顕微鏡で見たときの分類です。 大腸がんの多くは腺がんであり、腺がんはさらに細かい分類があります。 腺がん• 乳頭がん• 高分化型管状腺がん• 中分化型管状腺がん• 低分化型腺がん• 粘液がん• 印環細胞がん その他• 扁平上皮がん• 腺扁平上皮がん• その他 大腸がんの進行度(ステージ) 進行度は大腸がんの病気のひろがり具合を表します。 病変の深さ、どのリンパ節まで転移しているか、ほかの臓器に転移があるかどうかの3つを評価してステージ0から4まで分類します。 一般的に数字が大きくなるにつれ病気のひろがり具合が広いことを表しています。 大腸がんの場合は簡単に表現すると、病変が粘膜の中にとどまっていればステージ0、固有筋層までにとどまっていて リンパ節転移がない場合ステージ1、粘膜筋層よりも深いところまでひろがっているもののリンパ節転移がないものをステージ2、リンパ節転移はあるが遠隔転移はないものをステージ3、遠隔転移があればステージ4となります。 大腸がんのステージ別5年生存率 5年生存率とは 5年生存率は正式には5年相対生存率といいます。 病気ごとの治療効果を表現するための数値で、性別や年齢の条件を同じにそろえた上で、交通事故などほかの事故や病気で亡くなる数を取り除き、大腸がんのある人とない人の5年後の生存数を比較したものです。 5年生存率が100%に近ければ近いほど治療効果の高い病気、0%に近ければ近いほど治療効果が出にくい病気ということになります。 がん全体の5年生存率は男性で59. 1%、女性で66. 0%、全体では62. 1%でした(2006~2008年のデータ)。 大腸がんの5年生存率はどのくらいあるか 2006~2008年の大腸がんの5年生存率は男性で72. 2%、女性で69. 6%とがん全体と比較してやや良い数値でした。 ステージ別での5年生存率は ステージ1と2あわせて:96. 6% ステージ3:72. 1% ステージ4:15. 8% と報告されています。 ステージ3になるまで、つまりリンパ節転移する前に治療する事ができれば、かなり高い5年生存率が得られるということになります。 リンパ節転移をしていても遠隔転移がなければ7割近い5年生存率が得られます。 ステージ4になると5年生存率はかなり低下しますが、同じステージ4でも転移の部位によっては手術によって完治を望める場合もあり、 あくまで5年生存率は目安と考えて下さい。 ステージ4の平均余命とは 平均余命とは同じ病気の人が100人いたとき、半分の50人が亡くなる時期を示します。 100人の患者の生存期間をすべて足して人数で割った「平均」ではないことに注意が必要です。 患者や家族にとっては平均余命はとても気になる数字ですが、がんに対する治療効果を判断するのは平均余命ではなく5年生存率です。 平均余命はあくまで目安であり、かなり幅がある数字であることを知っておきましょう。 大腸がんステージ4の平均余命 大腸がんステージ4の平均余命は九州大学病院のグラフによると約20カ月です。 このデータは大腸がん以外で死亡した人も含んでいます。 ステージ4の生存率は36か月(3年)で25%まで徐々に低下しており、ざっと1カ月に2%ずつ低下するグラフとなっています。 罹患数と死亡数の推移 罹患数の推移 国立がん研究センターの報告では1985年を基準の1. 00とすると、1990年の罹患率は1. 5、2000年は2. 2、2010年は2. 8とかなりの増加傾向にあります。 将来の予測データでは2039年までの罹患数はほぼ横ばいと推測されていますが、年齢別でみると75歳以上の患者数は20年で約1. 37倍になると推測されています。 死亡数の推移 1960年に約5,000人であった大腸がんの死亡数はその後増加し1973年ごろには年間1万人、1986年には2万人、1995年には3万人、2004年には4万人、2016年には年間5万人を突破しました。 年齢調整を行い高齢化の影響を取り除いたデータでは人口10万人あたりの死亡者数は1980年で12. 8でしたが、1990年には20. 2、2003年30. 8、2016年40. 1まで増加しています。 大腸がんの末期症状とケアに関して 大腸がんの末期症状 大腸がんの末期症状としては大腸の病変が大きくなることによる 腹痛、吐き気、便秘、下痢、腹部膨満感などがあります。 また、病変が大きくなって便の通過が困難になると、腸閉塞(イレウス)の状態になり、頻回な嘔吐も見られるようになります。 さらにがん組織はとてももろいので容易に出血して、下血がみられ、貧血が進行することもあります。 お腹のあちこちにがん細胞がある場合には腹水が増えて、お腹が膨らむこともあります。 大腸がん末期のケアについて 大腸に対する処置 大腸の病変が大きくなり便が病変部位を通過できなくなった場合、腸の中に便や腸液、ガスが貯まって腸閉塞の状態になります。 食事をしなければ腸が詰まってもそのような状態にはならないのでは、と思われるかもしれませんが、全く飲んだり食べなかったりしても腸液はたまるので、腹痛や腹満感、頻回な嘔吐、ときには腸管が破裂して命にかかわる状態になる可能性もあります。 このような時には 人工肛門の手術やステント留置が行われます。 人工肛門とは腸の途中をお腹の表面に出して人工的に便の出口を作る手術で、病変よりも手前(口側)の腸で人工肛門を作れば便や腸液、ガスが体外に出されて腹痛や頻回な嘔吐といった症状は出にくくなります。 手術ではありますが、全身状態によっては局所麻酔で行うことができます。 ステント留置は腸の狭くなった部分に金属で作られた筒を挿入して中の通りを確保する方法で、こちらは大腸カメラを使って、腸の内側から治療することができますが、病変の位置によってステントが使える場所と使えない場所があります。 一旦ステントで中の通りが改善しても、病気の進行によりステントの中に病変が入り込んで再び腸閉塞になることもあります。 大腸がんの治療として手術の適応がない場合でも、大腸がんから出血したり、腸に穴が開いて寿命を縮める可能性があるときは、そのような事態を避けるために大腸の病変だけ切除することもあります。 全身に対する処置 痛みについてはほかのがんと同様に、 医療用麻薬などを用いて痛みを取り除く治療が行われます。 食欲不振や吐き気についてはその症状を和らげる薬が使われます。 栄養状態が悪いときには点滴で栄養を補うこともあります。 そのほか精神的な不安が強い場合は、不安を和らげる薬を使うこともあります。
次の