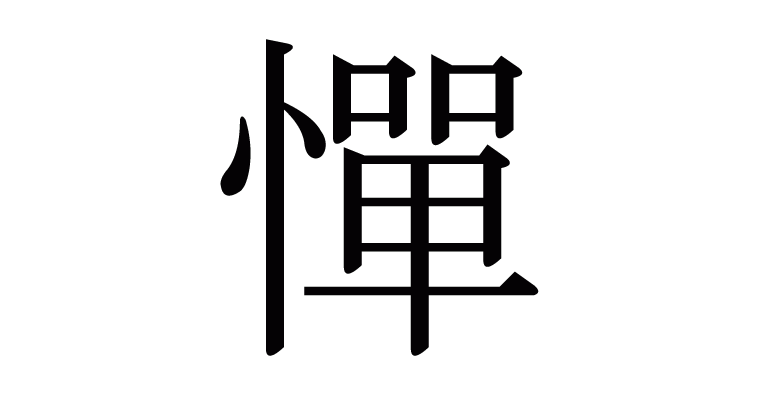漢字を部首の画数から検索

[chapter:あけとくれ] 「おおい、開けとくれ」 扉の向こうからは、あの男の声がする。 夕立に降られて濡れそぼった犬みたいに、どうにも情けなさを感じる声だ。 「開けとくれやい、達磨、達磨や」 こちらを呼んでいる。 あの男の声がする。 「開けて、開けとくれよ。 達磨くん、達磨くんよぉ」 どん、と戸を叩く音。 自らを知らせる音。 「開けて、開けとくれよぉ。 後生だから、開けとくれよぉ」 どん、どん。 「開けて、あけて」 どんどん、どんどん。 「開けて開けて開けて開けて開けてあけてあけてあけてあけてあけてあけてあけてあけて」 どんどん。 どんどんどんどん。 どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんっ!! 恐怖達磨が扉に手をかけた、その時だった。 「おい、達磨の。 開けンじゃねぇぞ。 アレは黄泉の門だ。 開けたら最期、おっ死ぬぞ」 扉の向こうと同じ声で、絶頂亭淫太郎はそう言った。 「ちょっと、絶頂亭さん! いい加減にしてくださいよ!」 恐怖達磨は開口一番、淫太郎に向かってそんなことを叫んだ。 「あン? 達磨やい、久しぶりに顔出したと思ってみりゃあ、随分なご挨拶じゃねェか」 「こっちだってアンタのせいでここ最近寝れなくて困ってたんだ! そりゃあ文句のひとつやふたつ出てくるってもんですよ!」 「ほォ、夢枕にでも俺が立ったか。 嬉しいねェ達磨の。 お前の寝苦しむ姿はさぞかし見ものなンだろうなァ」 文句を言われているにもかかわらず、男は下卑た笑いを浮かべる。 相も変わらずな男の姿に少し怯みながらも、しかし恐怖達磨はずいぶんと腹が立っていたのかなおも噛み付いた。 「毎日毎日、人の家の扉を叩いてきて! 誰かと思えばようやく喋ったな! アンタ、よっぽど暇人みたいですねぇ!」 「毎日毎日、ねェ……達磨や、お前ちょいと落ち着けってンだよ」 「なにがですか」 「お前よォ、俺が本当にお前の家まで毎日毎日、扉を叩きに来てるなンて思うのか。 まるで逢引みてェに。 珍しい客が逝杉屋に来たッてんで話聞いてりゃ、そりゃ少しばかり理不尽ってモンよ?」 「そ、それは……」 「だいたいだ。 お前の家、いったいドコにあると思ってンだ」 そこまで言われて、恐怖達磨はぐぅと閉口してしまう。 確かにこの男の元へ来るまでに、恐怖達磨はバスと市電を乗り継いではるばる千駄ヶ谷の見世物小屋へ赴いたのだ。 仮に、いくら憎しと思う相手でも、毎日そうしてまで通うだろうか。 ばつの悪そうに唇を噛む恐怖達磨に、淫太郎は眼鏡の奥の瞳をニヤリと細めた。 「ホレ見ろってンだ。 でもまァ、話くらいは聞いてやるから言ってみろやい。 それとも何かい、言うだけ言っておいてハイそうですかって引き下がるなんざ、まさかそんな手前勝手な真似しないよなァ?」 いよいよこうなると逃げ場もない。 自分の勘違いだと言い出すには遅い。 しかし、それでもわざわざ遠出して、来たくもないこの男の前までやっていたのだ。 得るものがないと引っ込みがつかない。 恐怖達磨はここ数日の奇妙な出来事を、ぽつりぽつりと話始めた。 隠居して久しい男が、すっかりと自分の身の上の奇譚を話し終える。 淫太郎はふむと考えると、ぱんと手を打って鳴らした。 「そンじゃ、今からお前ン家行くから」 「ハァ!?」 「今日は舞台演目も無いから、夜の仕舞いが早いンだ。 ちょうど良い」 言うが早く、淫太郎はいそいそと身支度を始める。 ああでもないこうでもないと、手近な従業員に指示を飛ばすと、それじゃあ行くかと恐怖達磨の背後についた。 「えっ、だって、その……」 「つべこべ言うなっての。 あ、でも途中でチョイと寄り道するぜ。 良いだろい」 あれよあれよという間に押し切られて、恐怖達磨はなぜだか文句をつけにいったはずの男を、自宅へと連れ帰ることになったのだった。 それが、今日の昼過ぎの話。 そして夕方が過ぎ、とっぷりとした夜がやってきた。 恐怖達磨は秋めいてきた夜風に寒さを覚えて、囲炉裏に火をくべる。 その囲炉裏を囲む男があとふたり。 「寄り道って、どうして大神さんまで連れてきたんですか」 「こういうのはスケさんのが詳しいンだ。 なァ、スケさんよォ」 熱燗を傾けていた大神スケキヨは、そうだねえと答える。 「ま、面白そうだったし。 ちょうど暇してたからね」 「てかアンタ、なに人の台所で勝手に熱燗作ってるんですか」 「良いじゃない良いじゃない。 秋の夜長は冷えるんだからサ」 「おうスケさん、俺にもくれや」 「ちょっとだけよー淫ちゃん」 家主のことなど露知らず、ちょっとした酒盛りを始める客人たちに恐怖達磨はハァと溜息を吐く。 結果として今回の悩みのタネを、このふたりに任せる事態になったのだが、正直不安だった。 実際、淫太郎が家に来るだけでも相当心に思うものはあるのだが、大神も一緒となると余計にさまざまな感情が去来する。 だがどちらか一方とひとつ屋根の下で夜を明かすことになるよりは、まだふたりのほうがマシだとも言えた。 「ところで達磨や、その音ってェのはどっからしてんだ。 もっぺん言ってくれや」 淫太郎の問いかけに、恐怖達磨は部屋の西側を指した。 「玄関です。 ここ数日、毎晩扉を叩きにくるんです。 最初は家鳴りかと思ったんですけど、あんまり酷いですし、それに夜にしか聞こえない。 誰か尋ねに来てるにしては夜更けというのもおかしい。 近所の子のいたずらかと思って、怒ってやろうと昨日は玄関で待ち構えてたんです。 そしたら」 「俺の声がした、ってか」 はい、そうですと淫太郎に向かって恐怖達磨が答える。 「絶頂亭さんの声が、扉の向こうからしたんです。 開けてくれ、って」 「開けたのかい」 「まさか。 開けませんよ」 あんたをウチにあげるつもりもなかったんだ、という本音を恐怖達磨はグッと飲み込んだ。 うなずきながら話を聞いていた大神が、熱燗を空けつつ口を挟む。 「そりゃあ賢明だね、達磨ちゃん。 それと淫ちゃん。 きっと今日、来るよ」 「来るって……淫太郎さんがですか?」 「アア、そうよ。 そりゃあそうよ。 ま、淫ちゃんかって言うと、チョット違うっていうかね」 わけがわからない、と首をかしげる恐怖達磨に対して、大神は酒の最後のひとしずくを舌で受け止めてから、予言めいて告げた。 「待ってれば分かるサ。 今どうこうしようったって、どうしようもないんだ。 今晩はおとなしくしてようや」 投げやりのような言葉にますます不安の募る恐怖達磨だったが、肝心の淫太郎が何も言わなかったので、そういうものかと自分を納得させた。 酒を飲んだふたりはすっかりと寝こけてしまった。 本当に、何のために来たんだろうかこの人たちは。 いびきをかく男たちを横目で見ながら、恐怖達磨は小さくなりゆく囲炉裏の火を見つめていた。 恐怖達磨の肩がびくりと跳ねる。 玄関扉を叩く音。 ここ数日聞いていたものだ。 嗚呼、もう彼らなどあてにならない。 自分ひとりでどうにかせねば。 恐怖達磨は押し入れの奥にしまい込んでいた日本刀を携えると、燭台の灯りを手に持って、彼は玄関へと向かった。 どん、どん。 相変わらず玄関が鳴っている。 どん、どん。 扉の向こうに立つ何かが、硬く握った拳で叩いている。 そんな姿が恐怖達磨の脳裏に浮かぶ。 いたずらにしてはタチが悪い。 ならばもしやとよぎるのは「怪異」という文字だ。 扉一枚隔てた向こう側に怪異が居るのか。 ならば少しばかり見てみたい気もする。 首をもたげる感情は、ここ数日の寝不足のせいだろうか。 夜が暗いせいで、扉の向こうの人影は分からない。 そもそも居るのかすら曖昧だ。 声をかけようかかけまいか、迷っていたその時だった。 「おおい、開けとくれ」 扉の向こうから、絶頂亭淫太郎の声がした。 夕立に降られて濡れそぼった犬みたいに、どうにも情けなさを感じる声だ。 あの男なら絶対に出さないような、哀れみめいた響きだった。 「開けとくれやい、達磨、達磨や」 淫太郎の声がこちらを呼ぶ。 開けてくれと懇願する。 懇願とはほど遠いような男の声で。 「開けて、開けとくれよ。 達磨くん、達磨くんよぉ」 どん、と戸を叩く音が強まる。 向こう側が主張する。 「開けて、開けとくれよぉ。 後生だから、開けとくれよぉ」 どん、どん。 強まっていく。 「開けて、あけて」 どんどん、どんどん。 「開けて開けて開けて開けて開けてあけてあけてあけてあけてあけてあけてあけてあけて」 どんどん。 どんどんどんどん。 妙に、そんな気持ちが湧いた。 恐怖達磨が扉に手をかけた、その時だった。 「おい、達磨の。 開けンじゃねぇぞ。 アレは黄泉の門だ。 開けたら最期、おっ死ぬぞ」 背中から飛んできた声に、恐怖達磨は振り返る。 そこには寝こけていたはずの、淫太郎が立っていた。 「あれ……?」 扉の向こうにいるはずの彼が、なぜここにいるのだろうか。 だって、だって自分は、ここを開けてやらねばならないのに。 扉の向こうで彼が待っているというのに。 「オラ、シャキっとしやがれってンだ。 目ェ覚ませよ、達磨やい」 淫太郎が大きな両手を恐怖達磨の前に持ってくる。 そしてすぐ鼻先で、ぱんっと柏手を打った。 「うわッ!」 「気ィしっかり持てよ。 じゃねェと、呑まれるぞ」 「えっ、あれ……なんで、絶頂亭さん?」 「こんな気味悪ィ気配、赤子でも起きらァ」 淫太郎の言葉をかき消すように、どん、と扉が大きく叩かれた。 びくりと身体を跳ねさせて、恐怖達磨が振り返る。 視線の先には玄関扉がある。 先ほど自分は何をしようとしていた。 なぜここを開けようとしたのか。 考えずとも分かることだ。 寝こけていたはずの淫太郎が、扉を叩いてくるわけがないのに。 悪い酔いから覚めるみたいに、頭がはっきりとしていく。 同時に、嫌な寒気がぶわりと肌を粟立たせた。 扉の向こう側はなおも、叩きながら懇願している。 「あけてあけて、あけて、あけておくれよぉ」 「ヒッ!」 短く悲鳴を上げて、恐怖達磨が扉から遠ざかる。 叩く力はどんどんと強さをまして、今にも叩き壊そうとするほどだ。 呼ぶ声にさまざまな色が混ざる。 男とも女とも、子どもとも老人ともつかない色で、声が呼ぶ。 「オウオウ、死人にしては威勢が良いなァ。 そんなにコチラが恋しいかよ」 怯える恐怖達磨の隣を抜けて、淫太郎が扉の前に立つ。 「帰る場所も無ェのなら、大人しくくたばってろ。 テメェのさみしさくらい、テメェでどうにかしやがれってンだよ」 ばんっ! 扉が強く叩かれる。 それは抗議なのか、なんなのか。 「俺ァ人間が大好きなンだよ。 生きてる人間の全部が好きなんだ。 だから、だからよォ。 テメェみたいなのは、お呼びじゃねェんだ」 ばんっ、ばんっ、ばんっ。 ひときわ大きく扉が叩かれると同時に、恐怖達磨の持っていたロウソクが、風もないのにふつりと消えた。 完全なる闇の中で、けたたましく音ばかりが響く。 ばんっ! ばんっ! ばんっ! 誰だって震え上がるような音を前にして、なお淫太郎は一切の恐れなどないように、恐怖達磨の前に立っていた。 「おい、達磨」 「な、なんですか」 闇の中で男の声が響く。 「ヘタな情けはかけるなよ。 背負いきれないモンは、自分が潰されっぞ」 「そんなの……かけるわけないでしょう」 「なら、いい」 このとき、淫太郎がどんな表情をしていたのか。 彼の背中しか見えなかった恐怖達磨にはわからなかった。 結局、その声と音は一晩中続いた。 しかし時が経つにつれて声は失せていき、戸を叩く音は弱まり、東から太陽が顔をのぞかせることには、もう跡形もなく消え去っていた。 一睡も出来ずにうろんとする頭で土間に戻ると、ちょうど目が覚めただろう大神があくびをひとつ零しつつ迎える。 「やあ、おはよう。 淫ちゃんに達磨ちゃん」 「大神さん……よく寝られましたね」 「へえ、何かあったかい?」 「えぇ……嘘でしょう」 「ところでさあ、喉乾いちゃったんだけど水とかお茶とか貰えないかな」 「アンタ自由か」 言っても仕方ないのは分かっていたので、恐怖達磨は全員のぶんのお茶を淹れて渡した。 三人で茶を飲む間、恐怖達磨は昨日のことのあらましを大神に伝えた。 ふむふむ、としばらく聞いていた大神だが、やがて話が終わるとおもむろに立ち上がった。 「サ、そんじゃ行きますか」 「おっ、行くかいスケさん」 「達磨ちゃんが朝餉出してくれるっていうなら話は別だけど、そんな感じじゃないし、だったらサッサと終わらせて東京駅周りのモーニングでも食べに行ったほうが良いってモンよ」 ふたりで交わされる合意に、恐怖達磨だけが置いてけぼりだった。 「行くって、ドコへ行くんですか?」 「ンー、行くっていうか、探すっていうかサ。 ところで達磨ちゃん」 「はい」 「ここの庭に、花は咲いてるかい?」 素っ頓狂なことを言う大神に、恐怖達磨は首をかしげながらも肯定を示した。 朝も早い頃。 三人は恐怖達磨の家の近くの山へと分け入っていた。 交通用の山道があるので歩きやすいが、いったいどうしてこんな場所に来ているのか、恐怖達磨には不思議でならなかった。 「そろそろ教えてもらっていいですかね。 大神さん、絶頂亭さん」 何か探しものでもするように、時々近くの茂みを探して歩くふたりに恐怖達磨が問いかける。 彼の片手には、庭に咲いていた桔梗の花束が握られている。 「今さ、お彼岸じゃない」 「そういえば、そうですねぇ」 「お彼岸の時期ってのはね、此岸と彼岸が最も近付く時期だって言われてるのよ。 つまり、この世とあの世が最も近い時期なの。 そんなときっていうのは、コッチとアッチの境目が曖昧になる。 ま、だからコッチ側の人間が、あの世に近づいてお参りするのが、お彼岸参りなワケなんだけどサ」 話す彼らに淫太郎の声が飛ぶ。 「オオイ、あったぜスケさん。 言ったとおりだ」 大神と恐怖達磨が近づけば、山道脇の草の根をかき分けて淫太郎がそれを指し示す。 意図的に積み重ねられた石が打ち捨てられていた。 アッ、と恐怖達磨が気付いたように声を上げる。 「これ、無縁仏……ですか」 「うん。 そうだよ、達磨ちゃん」 打ち捨てられていたものの、それは確かに墓の形をしていた。 「せっかくだからさ、達磨ちゃんが供えておやりよ」 大神に促されて、恐怖達磨は持ってきた桔梗を墓の前にそうっと置いた。 「だから花があるかって聞いたんですね、大神さんは」 「うん」 「これ……どこまで分かってたんですか」 「さあて、どこまでだろうねえ」 ケラケラ笑う大神に、食えない男だと眉を顰める。 恐怖達磨は目の前の墓石に手を合わせて、目を閉じて、それから目を開けて立ち上がった。 もういいだろう、と誰ともなく三人は墓を背にして帰路につく。 「しかしよォ、スケさん。 なんでこの死人は達磨なんざのところへ来たのかねェ」 「この道はまっすぐ達磨ちゃんの家に通じてるからね。 人気のない怪しい男の家が、ちょうど良かったんじゃないかなあ。 それに存外、達磨ちゃんも寂しがり屋だし」 「ほォん、なるほどな」 「それにさあ、達磨ちゃんってばお人好しっていうか、押しに弱そうじゃない?」 「アア、そらァ確かに!」 勝手気ままにのたまう男たちに向かって、恐怖達磨が言った。 「そんなことないですよ。 おれ、思われてるよりもお人好しなんかじゃないです。 誰かの寂しさを背負えるほど、強くもないです」 それに、と。 「なにせ、アンタたちみたいなのが、おれの友人なんですから」 言われて、それもそうかと、大神と淫太郎は顔を突き合わせてゲラゲラと下卑て笑った。 了 [newpage] [chapter:芒に良月、菊に盃] 「やァ、スケさんや。 ちょいと一杯どうだい?」 一升瓶に盃をふたつ手にした男は、月が昇るころそんなことを言い出した。 「今日は良い月だ。 飲み干してやろうや」 「淫ちゃんと飲むなんて、お月様と盃を交わすみたいだね」 「ア? どういうこったい?」 「いやいやいや、こっちの話。 ところで淫ちゃん、そりゃあアレかい、米の酒かい?」 「おうよ。 俺ァコッチのほうが好きでね」 「いいねえ。 世間様じゃ新清酒なんてモンが出回ってるようだけど、俺もね、昔ながらの米のお酒のが好きだね」 どうせならよく見えるところへ行こう、とふたりして縁側へと腰を据える。 絶頂亭淫太郎は持ってきた盃の一方を大神スケキヨへと渡す。 きゅぽん、と軽快な音を立てて栓を開けると、その逞しい腕で瓶を掲げた。 「そら、スケさんや」 大神は盃を向ける。 音を立てて注がれる透明な液体。 満ちた器を覗きこめば、丸く明るい月が浮かんでいた。 淫太郎もまた自分の盃に酒を注ぐ。 頃合いを見て大神が、満ちた盃を少しだけ上に掲げてから口を付けた。 「こりゃあいい酒だねえ。 淫ちゃん、どしたのさコレ」 「ンー、なんか飲みたくなってな。 近くの酒屋でちょっくら調達してきたのサ」 適当に見繕ってきたのだろう。 そのわりには中々良い酒だ。 芳醇な甘みある香りを漂わせながら、水のように口当たりがよい。 するりと飲めてしまう。 店が良いのか店主が良いのか、あるいは淫太郎の天性の勘のようなものか。 どちらにせよ素晴らしいと、大神は舌鼓を打った。 「しかし淫ちゃんが月見酒なんて、意外だね。 何かあったのかい?」 「え、アア……そういや今日は月見か。 コロっと忘れちまってたなァ」 ただな、と淫太郎が盃を傾けながら言う。 「風流なんざ分からんが、妙にざわつくんだよ。 こんな月の夜は。 拐かしでも切断でも足りねェ。 もっともっと、大事なモンをどうにかしてやりたくなる。 けど学者サマでも何でもない俺にゃあ検討がつかないってモンで、こうして酒を飲んでは独り鎮めるのサ」 「へえ、そうかい」 隣で酒を舐めながら、まるで獣だと大神は思う。 月に狂いたる獣。 剥き出しの魂で咆えるその姿。 本能を隠さず、むしろ見世物にすらして生きる彼という名の劇場。 笑みの絶えない横顔は、獲物を定める野生の獣によく似ている。 「淫ちゃんはサ、なんていうか獣だよね。 素直に生きている。 本能のままだ」 「ほォン、ヘェ……」 「清々しくて、見てて気持ちいいよ」 その孕んだ苛烈が。 ヱンターテヰメントとして昇華された慟哭が。 などという含みを持たせたまま、大神が一杯目の盃を空けた、その時だ。 突然、大神の視界に夜があふれた。 黒雲に陰る月。 墨を零したような空。 それと、屋根の終わり。 「俺を獣と測るかい、スケさん」 背中に当たる冷えた床の感触に、自分が仰向けに転んでいるのだと大神は気付く。 よもや一杯程度で前後を失うほど酒に弱くもない。 胸のほうから、ぞわりと這い寄る声がする。 「だったらそいつァ検討違いサ」 熱い温度が、胸を、首を昇ってきて、大神の覆面の隙間に侵入する。 太い指がケロイドの皮膚を舐めるように撫でて、覆面の下半分を勢い良くめくり上げた。 秋の夜風が、隠された皮膚を冷たく暴く。 月に晒された醜さに、淫太郎は情夫へ向ける視線と見紛うほど、うっとりと目を細めた。 「俺が本当に獣なら、とっくにその喉元に噛み付いてるところさァ。 なんてったってスケさんや、アンタは俺好みの顔をしてるンだから」 夜を背負う男の眼差しの、その淫蕩せし狂気の輝きといったら! 淫太郎の大きな手が、大神の喉を掴む。 そのまま上下にゆうるりと、愛おしそうに撫でた。 けれどもこの男が、そのままの温度で首をへし折れるのを、大神は知っている。 男の肩越しに大神は月を見上げた。 澄み渡る秋の月は、磨き上げた牙の輝きにも似る。 「でも、スケさんを見世物にするにゃあ、ちと惜しいや」 淫太郎の手が離れる。 ほんの少し名残惜しそうに思えたのは、大神の思い過ごしか。 「ところでよォ、スケさん。 盃が乾いちまいそうだ」 首をひねって見れば、盃を弄ぶ淫太郎と、自身と彼の間にある一升瓶が見えた。 だからこそ魅せられてしょうがないのだろう。 彼の見世物に。 大神は心底面白そうに口元を歪めて、それからよいしょと起き上がった。 「そうだね、俺が見誤ってたよ。 淫ちゃん、アンタは獣なんかじゃない。 それよりもなお凄まじい何かだ。 達磨ちゃんの言葉を借りれば、妖怪ってヤツなのかねえ」 「俺がそンなのに当てはまるかってンだ」 「じゃあ、やっぱり月だね。 見る時によってコロコロ変わって、闇でだけ光る」 「月と月見たァ、洒落てるねェスケさん」 おかしそうに笑う男に、大神は心中の冷や汗を拭う。 喰われなくて良かった。 「サテと、そんじゃあ続きといきましょうか。 淫ちゃん」 大神は淫太郎の空いた盃に酒を注ぐ。 なみなみと、酒の水面が揺れた。 「じゃあ、俺も注いでやらァ」 「ありがとね」 手から転がった盃を拾って差し出す。 月より注がれる酒は、光を受けて銀色に輝いた。 満ちた器を覗きこめばやはり、そこには丸い月がある。 「夜も酒もこれからよ。 楽しくやろうや」 淫太郎が一息に酒をあおるのを見届けてから、大神も月を飲み干した。 了 [newpage] [chapter:恨みの仮面] へェ……お客さん。 その見世物が気になるンで? アア、いやいや怪しいモンじゃあござァせん。 僕はこのチンケな見世物小屋のオーナーなんてものをやらせて頂いてる者です。 ア、いやいや名乗るほどのモンじゃあない。 そうさなァ……オーナー、とでもお呼びくだせェ。 そうそう、その見世物ですがね……はァ……ほォン……確かに、傴僂や犬を食う見世物に比べちャア、華も欠けるってぇモンですな。 ですがお客さん、その見世物はこの小屋でもトクベツなンですぜ。 この小屋の見世物は『覗く』のがほとんどでゲスが、こいつァちょっと色が違う。 どう違うかって? それはこれからのお話よ。 お客さんも見ての通り、一見すると普通の半面だ。 獣だか骸だか鬼だか定かじゃねェ。 それってぇのも、この仮面、日ノ本に正真正銘ただ一品の珍品なんでサァ。 とある男の憐れましくもおぞましい物語の、その成れの果てがお客さんの目の前のこの仮面ってぇコトよ。 アア、慌てなさんな。 物事には順序ってェモンがあるんでサ。 ちゃあんとお話するんで、お代は聞いてのおかえりよ。 ある田舎に男がひとりいた。 男ァすくすくと立派に育ち、ついに戦争へ旅立つ年頃になった。 男は言った「おかあさん、立派に戦って参ります」おっかさんはそりゃあ涙しながらもハンケチを振って見送ったものサ。 さて戦争のドンパチやと思った矢先のコトだ。 男は軍の訓練射撃中、悲運にもサンパチの暴発を食らっちまって、顔にひでぇ火傷とケロイドをこさえちまった。 オマケに視力も下がったモンだから、兵役からも外されちまう。 ノコノコ背中丸めて帰った男の姿に、田舎のおっかさんは卒倒した。 送り出した息子が……ふた目と見られぬ傷をこさえて帰ってきたんだ。 しかも敵国のあんちきしょうも殺してねェ、まっさらなカラダで。 男はたちまち近所でウワサになった。 人も殺せぬ化物が、某さんの家に帰ってきたァなんて。 気付けば男は鼻つまみ、親族一同からも村八分。 いやこれこそ人間の汚らしさたるや。 すさまじさたるや。 イヤァおぞましいねェ。 俺ァ人間が何よりも怖いでげすよ。 ナンテ……それは置いといてだ。 化物じみたこの男が、いよいよ心まで修羅に成り果ててしまいそうな、ある夜のことよ。 男は庭先から何かの気配を感じたのよ。 障子をそうっと開けて庭を覗き見た男は、ハッと小さく息を飲んだ。 そこにはとっぷりとした夜闇を集めたような、異形の姿があったんだ。 獣とも骸とも鬼ともつかぬその異形は、男を見るとニヤリ、と気味悪く嗤って、煙のように消えっちまった。 異形は擦り切れた男の精神の見せた幻覚だったのか、あるいは男の闇が呼び寄せた怪異であったのか……。 真偽のほどは定かじゃ無ェ。 次の日、お天道サンが昇ってからというもの、男は狂ったようにかの異形を掘り始めた。 セッセコセッセコ、庭の緑がぜぇんぶ埋まっちまうほど……朝から晩までサ。 そんなモンだから、男はついに頭がイカレちまったかなんて散々言われ放題だったが、なおも男は憑かれたように堀り続けたんだってサ。 しかし奇特な人間も世の中にャ居るモンで、こんな男を訪ねてはるばるやってくる者もチラホラ現れ始めた。 そのうち男は、自分のことをこう名乗るようになった。 『恐怖達磨』と。 魔除けか血塗れか、真っ赤な頭巾を被って……獣とも骸とも鬼ともつかぬ面をつける。 異形に魅せられた男が異形のような姿を取ったってェ話よ。 ……アア、いやいやお客サン。 この話にャまだ続きがあるってんで。 そうそう、お察しの通りこの半面こそが、『恐怖達磨』の面でサァ。 まァ今しばらくお聞きくだせェ。 この仮面に至る奇怪な逸話を。 この恐怖達磨ってェ男、ひょんなことから軽井沢で奇怪な事件に巻き込まれた。 そこから何の因果か、この事件で四人の男と知り合って、ケッコウ仲良くなったンだ。 たまに飲みに行ったり、銀座へ旨いモノ食いに行ったりとよ。 そうしてた、ある日だ……恐怖達磨と男達が酒を飲んでたンだ。 心地よく酔いも回った頃合いで、ひとりの男が言った。 「達磨ちゃん。 その仮面の下はいったいどうなってるんだい。 ちょっくら教えとくれよ。 もう俺たちも知り合って結構経つんだからサ」 他の男も口々に見せろ見せろと囃し立てた。 しかし恐怖達磨はいっこうに面を外そうとしない。 いやだいやだ、と褥を前にした生娘みてェにイヤがるってンで、ひとりの男がシビれを切らして、恐怖達磨に覆いかぶさり仮面を無理やりに剥がしたんだ。 いよいよランプの灯りの元にその醜い顔が晒されるかと、思った途端ヨ。 恐怖達磨はフッ、と煙みたいに消えちまったんだ。 本当に……煙みてェに。 あとには赤い頭巾と、ボロッ切れみたいな服と、仮面だけが残された。 さきほどまで飲み食いし……語らった男はもう、どこにも見当たらなかった。 残った男どもはああでもないこうでもないと考えたが、やがて辿り着いた答えがこうよ。 「恐怖達磨という男は、人心を怖れ怪異に魅入られたあまり、自分がほんとうの怪異になってしまったのだ」と。 ほうぼうを探し尋ねたが、やはり恐怖達磨という男はこの世からぷつりと居なくなっちまった。 とまァ、それが恐怖達磨っつー男の話ヨ。 サテお客さん。 長いことご拝聴下さりありがとうございやす。 しかしてあと一つ、聞いて欲しいモンがあるんでサ。 その、目の前の半面。 恐怖達磨の面に、よぅく耳を澄ましておくんなまし。 するとね、ホラ、聞こえるでしょう。 恐怖達磨の声が。 仮面から。 いんたろうさん、どうして、仮面をはずしてしまったんですか……って。 ヘヘッ、そうでございましょう。 いやァ、おかげで酌の相手にゃ困らなくてイイってモンですぜ……イヤそれはコッチの話でげす。 アア……いやマッタク……そう言われちゃあオシマイってモンですよ。 お客さん。 じゃあアチラの見世物はどうでしょう、世にも奇っ怪な首吊り続け男ですぜ。 首を吊って早十年、その年季は折り紙付き! ササッ、どうぞアチラへ……。 ……ふぅ、インチキだなんて見世物小屋に言うなんざ、洒落の分かンねェ客だなァ。 そうだろう、達磨や。 お前さん、こんなに小さくなっちまって。 アア、アア……そうさなァ。 またみんなで飲もうや。 スケさんや大山田先生や露助も誘ってよォ。 あン……なんだよお前さん、どうせならもちっと芸らしいこともしてみろってンだ。 そしたらお前の見世物も、こんなしみったれた名前じゃなくて、もっと気の利いた名前にでもするってェのによ。 ……何だよ達磨の、嗤ってンじゃねェよ。 まったくけったいな奴だなァ、お前も。 そら、次のお客が来るぜ。 どうせなら唄のひとつでも、唄ってみろよ。
次の