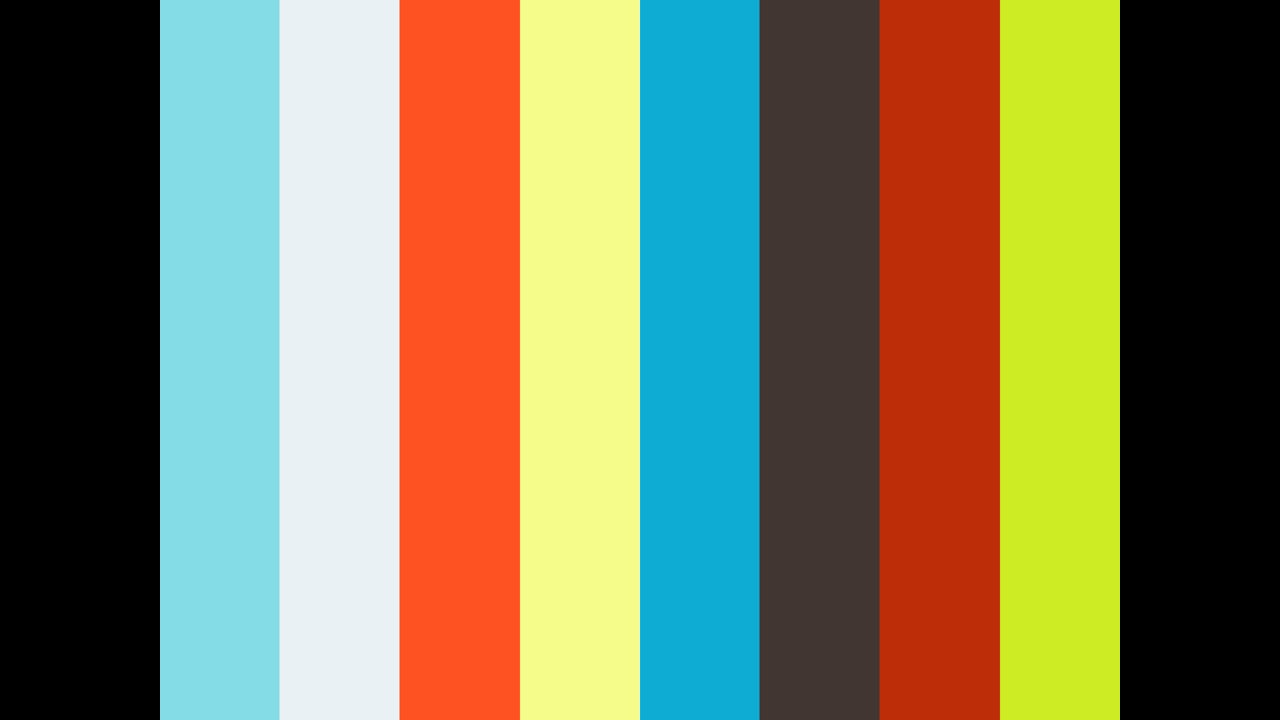古典 文法 助動詞 る
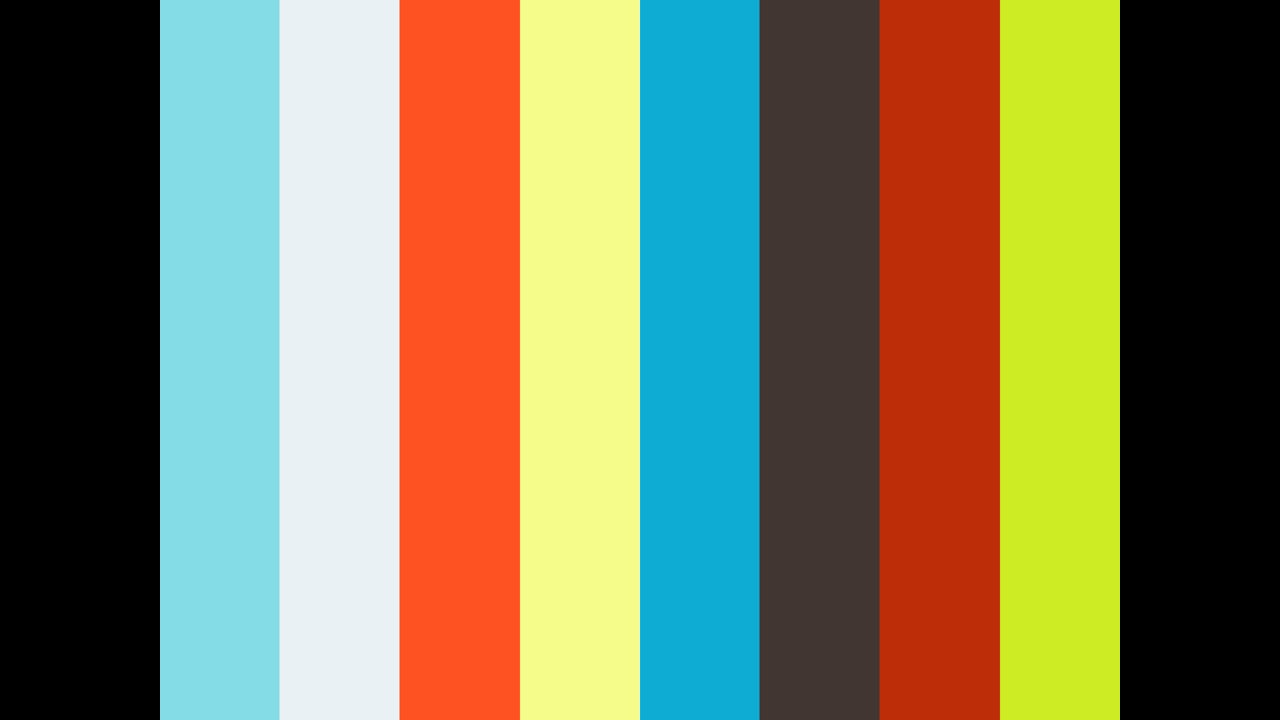
御車入るべき門は鎖したりければ、人して惟光召させて、待たせたまひけるほど、むつかしげなる大路のさまを見わたしたまへるに、この家のかたはらに、桧垣といふもの新しうして、上は半蔀四五間ばかり上げわたして、簾などもいと白う涼しげなるに、をかしき額つきの透影、あまた見えて覗く。 立ちさまよふらむ下つ方思ひやるに、あながちに丈高き心地ぞする。 いかなる者の集へるならむと、やうかはりて思さる。 御車もいたくやつしたまへり、前駆も追はせたまはず、誰れとか知らむとうちとけたまひて、すこしさし覗きたまへれば、門は蔀のやうなる、押し上げたる、見入れのほどなく、ものはかなき住まひを、あはれに、「何処かさして」と思ほしなせば、玉の台も同じことなり。 切懸だつ物に、いと青やかなる葛の心地よげに這ひかかれるに、白き花ぞ、おのれひとり笑みの眉開けたる。 「遠方人にもの申す」 と独りごちたまふを、御隋身ついゐて、 「かの白く咲けるをなむ、夕顔と申しはべる。 花の名は人めきて、かうあやしき垣根になむ咲きはべりける」 と申す。 げにいと小家がちに、むつかしげなるわたりの、このもかのも、あやしくうちよろぼひて、むねむねしからぬ軒のつまなどに這ひまつはれたるを、 「口惜しの花の契りや。 一房折りて参れ」 とのたまへば、この押し上げたる門に入りて折る。 さすがに、されたる遣戸口に、黄なる生絹の単袴、長く着なしたる童の、をかしげなる出で来て、うち招く。 白き扇のいたうこがしたるを、 「これに置きて参らせよ。 枝も情けなげなめる花を」 とて取らせたれば、門開けて惟光朝臣出で来たるして、奉らす。 「鍵を置きまどはしはべりて、いと不便なるわざなりや。 もののあやめ見たまへ分くべき人もはべらぬわたりなれど、らうがはしき大路に立ちおはしまして」とかしこまり申す。 引き入れて、下りたまふ。 惟光が兄の阿闍梨、婿の三河守、娘など、渡り集ひたるほどに、かくおはしましたる喜びを、またなきことにかしこまる。 尼君も起き上がりて、 「惜しげなき身なれど、捨てがたく思うたまへつることは、ただ、かく御前にさぶらひ、御覧ぜらるることの変りはべりなむことを口惜しく思ひたまへ、たゆたひしかど、忌むことのしるしによみがへりてなむ、かく渡りおはしますを、見たまへはべりぬれば、今なむ阿弥陀仏の御光も、心清く待たれはべるべき」 など聞こえて、弱げに泣く。 「日ごろ、おこたりがたくものせらるるを、安からず嘆きわたりつるに、かく、世を離るるさまにものしたまへば、いとあはれに口惜しうなむ。 命長くて、なほ位高くなど見なしたまへ。 さてこそ、九品の上にも、障りなく生まれたまはめ。 この世にすこし恨み残るは、悪ろきわざとなむ聞く」など、涙ぐみてのたまふ。 かたほなるをだに、乳母やうの思ふべき人は、あさましうまほに見なすものを、まして、いと面立たしう、なづさひ仕うまつりけむ身も、いたはしうかたじけなく思ほゆべかめれば、すずろに涙がちなり。 子どもは、いと見苦しと思ひて、「背きぬる世の去りがたきやうに、みづからひそみ御覧ぜられたまふ」と、つきしろひ目くはす。 君は、いとあはれと思ほして、 「いはけなかりけるほどに、思ふべき人びとのうち捨ててものしたまひにけるなごり、育む人あまたあるやうなりしかど、親しく思ひ睦ぶる筋は、またなくなむ思ほえし。 人となりて後は、限りあれば、朝夕にしもえ見たてまつらず、心のままに訪らひ参づることはなけれど、なほ久しう対面せぬ時は、心細くおぼゆるを、『さらぬ別れはなくもがな』」 となむ、こまやかに語らひたまひて、おし拭ひたまへる袖のにほひも、いと所狭きまで薫り満ちたるに、げに、よに思へば、おしなべたらぬ人の御宿世ぞかしと、尼君をもどかしと見つる子ども、皆うちしほたれけり。 修法など、またまた始むべきことなど掟てのたまはせて、出でたまふとて、惟光に紙燭召して、ありつる扇御覧ずれば、もて馴らしたる移り香、いと染み深うなつかしくて、をかしうすさみ書きたり。 「心あてにそれかとぞ見る白露の 光そへたる夕顔の花」 そこはかとなく書き紛らはしたるも、あてはかにゆゑづきたれば、いと思ひのほかに、をかしうおぼえたまふ。 惟光に、 「この西なる家は何人の住むぞ。 問ひ聞きたりや」 とのたまへば、例のうるさき御心とは思へども、えさは申さで、 「この五、六日ここにはべれど、病者のことを思うたまへ扱ひはべるほどに、隣のことはえ聞きはべらず」 など、はしたなやかに聞こゆれば、 「憎しとこそ思ひたれな。 されど、この扇の、尋ぬべきゆゑありて見ゆるを。 なほ、このわたりの心知れらむ者を召して問へ」 とのたまへば、入りて、この宿守なる男を呼びて問ひ聞く。 「揚名介なる人の家になむはべりける。 男は田舎にまかりて、妻なむ若く事好みて、はらからなど宮仕人にて来通ふ、と申す。 詳しきことは、下人のえ知りはべらぬにやあらむ」と聞こゆ。 「さらば、その宮仕人ななり。 したり顔にもの馴れて言へるかな」と、「めざましかるべき際にやあらむ」と思せど、さして聞こえかかれる心の、憎からず過ぐしがたきぞ、例の、この方には重からぬ御心なめるかし。 御畳紙にいたうあらぬさまに書き変へたまひて、 「寄りてこそそれかとも見めたそかれに ほのぼの見つる花の夕顔」 ありつる御随身して遣はす。 まだ見ぬ御さまなりけれど、いとしるく思ひあてられたまへる御側目を見過ぐさで、さしおどろかしけるを、答へたまはでほど経ければ、なまはしたなきに、かくわざとめかしければ、あまえて、「いかに聞こえむ」など言ひしろふべかめれど、めざましと思ひて、随身は参りぬ。 御前駆の松明ほのかにて、いと忍びて出でたまふ。 半蔀は下ろしてけり。 隙々より見ゆる灯の光、蛍よりけにほのかにあはれなり。 御心ざしの所には、木立前栽など、なべての所に似ず、いとのどかに心にくく住みなしたまへり。 うちとけぬ御ありさまなどの、気色ことなるに、ありつる垣根思ほし出でらるべくもあらずかし。 翌朝、すこし寝過ぐしたまひて、日さし出づるほどに出でたまふ。 朝明の姿は、げに人のめできこえむも、ことわりなる御さまなりけり。 今日もこの蔀の前渡りしたまふ。 来し方も過ぎたまひけむわたりなれど、ただはかなき一ふしに御心とまりて、「いかなる人の住み処ならむ」とは、往き来に御目とまりたまひけり。 惟光、日頃ありて参れり。 「わづらひはべる人、なほ弱げにはべれば、とかく見たまへあつかひてなむ」 など、聞こえて、近く参り寄りて聞こゆ。 「仰せられしのちなむ、隣のこと知りてはべる者、呼びて問はせはべりしかど、はかばかしくも申しはべらず。 『いと忍びて、五月のころほひよりものしたまふ人なむあるべけれど、その人とは、さらに家の内の人にだに知らせず』となむ申す。 時々、中垣のかいま見しはべるに、げに若き女どもの透影見えはべり。 褶だつもの、かことばかり引きかけて、かしづく人はべるなめり。 昨日、夕日のなごりなくさし入りてはべりしに、文書くとてゐてはべりし人の、顔こそいとよくはべりしか。 もの思へるけはひして、ある人びとも忍びてうち泣くさまなどなむ、しるく見えはべる」 と聞こゆ。 君うち笑みたまひて、「知らばや」と思ほしたり。 おぼえこそ重かるべき御身のほどなれど、御よはひのほど、人のなびきめできこえたるさまなど思ふには、好きたまはざらむも、情けなくさうざうしかるべしかし、人のうけひかぬほどにてだに、なほ、さりぬべきあたりのことは、このましうおぼゆるものを、と思ひをり。 「もし、見たまへ得ることもやはべると、はかなきついで作り出でて、消息など遣はしたりき。 書き馴れたる手して、口とく返り事などしはべりき。 いと口惜しうはあらぬ若人どもなむはべるめる」 と聞こゆれば、 「なほ言ひ寄れ。 尋ね寄らでは、さうざうしかりなむ」とのたまふ。 かの、下が下と、人の思ひ捨てし住まひなれど、その中にも、思ひのほかに口惜しからぬを見つけたらばと、めづらしく思ほすなりけり。 さて、かの空蝉のあさましくつれなきを、この世の人には違ひて思すに、おいらかならましかば、心苦しき過ちにてもやみぬべきを、いとねたく、負けてやみなむを、心にかからぬ折なし。 かやうの並々までは思ほしかからざりつるを、ありし「雨夜の品定め」の後、いぶかしく思ほしなる品々あるに、いとど隈なくなりぬる御心なめりかし。 うらもなく待ちきこえ顔なる片つ方人を、あはれと思さぬにしもあらねど、つれなくて聞きゐたらむことの恥づかしければ、「まづ、こなたの心見果てて」と思すほどに、伊予介上りぬ。 まづ急ぎ参れり。 舟路のしわざとて、すこし黒みやつれたる旅姿、いとふつつかに心づきなし。 されど、人もいやしからぬ筋に、容貌などねびたれど、きよげにて、ただならず、気色よしづきてなどぞありける。 国の物語など申すに、「湯桁はいくつ」と、問はまほしく思せど、あいなくまばゆくて、御心のうちに思し出づることもさまざまなり。 「ものまめやかなる大人を、かく思ふも、げにをこがましく、うしろめたきわざなりや。 げに、これぞ、なのめならぬ片はなべかりける」と、馬頭の諌め思し出でて、いとほしきに、「つれなき心はねたけれど、人のためは、あはれ」と思しなさる。 「娘をばさるべき人に預けて、北の方をば率て下りぬべし」と、聞きたまふに、ひとかたならず心あわたたしくて、「今一度はえあるまじきことにや」と、小君を語らひたまへど、人の心を合せたらむことにてだに、軽らかにえしも紛れたまふまじきを、まして、似げなきことに思ひて、今さらに見苦しかるべし、と思ひ離れたり。 さすがに、絶えて思ほし忘れなむことも、いと言ふかひなく、憂かるべきことに思ひて、さるべき折々の御答へなど、なつかしく聞こえつつ、なげの筆づかひにつけたる言の葉、あやしくらうたげに、目とまるべきふし加へなどして、あはれと思しぬべき人のけはひなれば、つれなくねたきものの、忘れがたきに思す。 いま一方は、主強くなるとも、変らずうちとけぬべく見えしさまなるを頼みて、とかく聞きたまへど、御心も動かずぞありける。 秋にもなりぬ。 人やりならず、心づくしに思し乱るることどもありて、大殿には、絶え間置きつつ、恨めしくのみ思ひ聞こえたまへり。 六条わたりにも、とけがたかりし御気色をおもむけ聞こえたまひて後、ひき返し、なのめならむはいとほしかし。 されど、よそなりし御心惑ひのやうに、あながちなる事はなきも、いかなることにかと見えたり。 女は、いとものをあまりなるまで、思ししめたる御心ざまにて、齢のほども似げなく、人の漏り聞かむに、いとどかくつらき御夜がれの寝覚め寝覚め、思ししをるること、いとさまざまなり。 霧のいと深き朝、いたくそそのかされたまひて、ねぶたげなる気色に、うち嘆きつつ出でたまふを、中将のおもと、御格子一間上げて、見たてまつり送りたまへ、とおぼしく、御几帳引きやりたれば、御頭もたげて見出だしたまへり。 前栽の色々乱れたるを、過ぎがてにやすらひたまへるさま、げにたぐひなし。 廊の方へおはするに、中将の君、御供に参る。 紫苑色の折にあひたる、羅の裳、鮮やかに引き結ひたる腰つき、たをやかになまめきたり。 見返りたまひて、隅の間の高欄に、しばし、ひき据ゑたまへり。 うちとけたらぬもてなし、髪の下がりば、めざましくも、と見たまふ。 「咲く花に移るてふ名はつつめども 折らで過ぎ憂き今朝の朝顔 いかがすべき」 とて、手をとらへたまへれば、いと馴れてとく、 「朝霧の晴れ間も待たぬ気色にて 花に心を止めぬとぞ見る」 と、おほやけごとにぞ聞こえなす。 をかしげなる侍童の、姿このましう、ことさらめきたる、指貫の裾、露けげに、花の中に混りて、朝顔折りて参るほどなど、絵に描かまほしげなり。 大方に、うち見たてまつる人だに、心とめたてまつらぬはなし。 物の情け知らぬ山がつも、花の蔭には、なほやすらはまほしきにや、この御光を見たてまつるあたりは、ほどほどにつけて、我がかなしと思ふ女を、仕うまつらせばやと願ひ、もしは、口惜しからずと思ふ妹など持たる人は、卑しきにても、なほ、この御あたりにさぶらはせむと、思ひ寄らぬはなかりけり。 まして、さりぬべきついでの御言の葉も、なつかしき御気色を見たてまつる人の、すこし物の心思ひ知るは、いかがはおろかに思ひきこえむ。 明け暮れうちとけてしもおはせぬを、心もとなきことに思ふべかめり。 まことや、かの惟光が預かりのかいま見は、いとよく案内見とりて申す。 「その人とは、さらにえ思ひえはべらず。 人にいみじく隠れ忍ぶる気色になむ見えはべるを、つれづれなるままに、南の半蔀ある長屋にわたり来つつ、車の音すれば、若き者どもの覗きなどすべかめるに、この主とおぼしきも、はひわたる時はべかめる。 容貌なむ、ほのかなれど、いとらうたげにはべる。 一日、前駆追ひて渡る車のはべりしを、覗きて、童女の急ぎて、『右近の君こそ、まづ物見たまへ。 中将殿こそ、これより渡りたまひぬれ』と言へば、また、よろしき大人出で来て、『あなかま』と、手かくものから、『いかでさは知るぞ、いで、見む』とて、はひ渡る。 打橋だつものを道にてなむ通ひはべる。 急ぎ来るものは、衣の裾を物に引きかけて、よろぼひ倒れて、橋よりも落ちぬべければ、『いで、この葛城の神こそ、さがしうしおきたれ』と、むつかりて、物覗きの心も冷めぬめりき。 『君は、御直衣姿にて、御随身どももありし。 なにがし、くれがし』と数へしは、頭中将の随身、その小舎人童をなむ、しるしに言ひはべりし」など聞こゆれば、 「たしかにその車をぞ見まし」 とのたまひて、「もし、かのあはれに忘れざりし人にや」と、思ほしよるも、いと知らまほしげなる御気色を見て、 「私の懸想もいとよくしおきて、案内も残るところなく見たまへおきながら、ただ、我れどちと知らせて、物など言ふ若きおもとのはべるを、そらおぼれしてなむ、隠れまかり歩く。 いとよく隠したりと思ひて、小さき子どもなどのはべるが言誤りしつべきも、言ひ紛らはして、また人なきさまを強ひてつくりはべる」など、語りて笑ふ。 「尼君の訪ひにものせむついでに、かいま見せさせよ」とのたまひけり。 かりにても、宿れる住ひのほどを思ふに、「これこそ、かの人の定め、あなづりし下の品ならめ。 その中に、思ひの外にをかしきこともあらば」など、思すなりけり。 惟光、いささかのことも御心に違はじと思ふに、おのれも隈なき好き心にて、いみじくたばかりまどひ歩きつつ、しひておはしまさせ初めてけり。 このほどのこと、くだくだしければ、例のもらしつ。 女、さしてその人と尋ね出でたまはねば、我も名のりをしたまはで、いとわりなくやつれたまひつつ、例ならず下り立ちありきたまふは、おろかに思されぬなるべし、と見れば、我が馬をばたてまつりて、御供に走りありく。 「懸想人のいとものげなき足もとを、見つけられてはべらむ時、からくもあるべきかな」とわぶれど、人に知らせたまはぬままに、かの夕顔のしるべせし随身ばかり、さては、顔むげに知るまじき童一人ばかりぞ、率ておはしける。 「もし思ひよる気色もや」とて、隣に中宿をだにしたまはず。 女も、いとあやしく心得ぬ心地のみして、御使に人を添へ、暁の道をうかがはせ、御在処見せむと尋ぬれど、そこはかとなくまどはしつつ、さすがに、あはれに見ではえあるまじく、この人の御心にかかりたれば、便なく軽々しきことと、思ほし返しわびつつ、いとしばしばおはします。 かかる筋は、まめ人の乱るる折もあるを、いとめやすくしづめたまひて、人のとがめきこゆべき振る舞ひはしたまはざりつるを、あやしきまで、今朝のほど、昼間の隔ても、おぼつかなくなど、思ひわづらはれたまへば、かつは、いともの狂ほしく、さまで心とどむべきことのさまにもあらずと、いみじく思ひさましたまふに、人のけはひ、いとあさましくやはらかにおほどきて、もの深く重き方はおくれて、ひたぶるに若びたるものから、世をまだ知らぬにもあらず。 いとやむごとなきにはあるまじ、いづくにいとかうしもとまる心ぞ、と返す返す思す。 いとことさらめきて、御装束をもやつれたる狩の御衣をたてまつり、さまを変へ、顔をもほの見せたまはず、夜深きほどに、人をしづめて出で入りなどしたまへば、昔ありけむものの変化めきて、うたて思ひ嘆かるれど、人の御けはひ、はた、手さぐりもしるべきわざなりければ、「誰ればかりにかはあらむ。 なほこの好き者のし出でつるわざなめり」と、大夫を疑ひながら、せめてつれなく知らず顔にて、かけて思ひよらぬさまに、たゆまずあざれありけば、いかなることにかと心得がたく、女方もあやしうやう違ひたるもの思ひをなむしける。 君も、「かくうらなくたゆめてはひ隠れなば、いづこをはかりとか、我も尋ねむ。 かりそめの隠れ処と、はた見ゆめれば、いづ方にもいづ方にも、移ろひゆかむ日を、いつとも知らじ」と思すに、追ひまどはして、なのめに思ひなしつべくは、ただかばかりのすさびにても過ぎぬべきことを、さらにさて過ぐしてむと思されず。 人目を思して、隔ておきたまふ夜な夜ななどは、いと忍びがたく、苦しきまでおぼえたまへば、「なほ誰れとなくて二条院に迎へてむ。 もし聞こえありて便なかるべきことなりとも、さるべきにこそは。 我が心ながら、いとかく人にしむことはなきを、いかなる契りにかはありけむ」など思ほしよる。 「いざ、いと心安き所にて、のどかに聞こえむ」 など、語らひたまへば、 「なほ、あやしう。 かくのたまへど、世づかぬ御もてなしなれば、もの恐ろしくこそあれ」 と、いと若びて言へば、「げに」と、ほほ笑まれたまひて、 「げに、いづれか狐なるらむな。 ただはかられたまへかし」 と、なつかしげにのたまへば、女もいみじくなびきて、さもありぬべく思ひたり。 「世になく、かたはなることなりとも、ひたぶるに従ふ心は、いとあはれげなる人」と見たまふに、なほ、かの頭中将の常夏疑はしく、語りし心ざま、まづ思ひ出でられたまへど、「忍ぶるやうこそは」と、あながちにも問ひ出でたまはず。 気色ばみて、ふと背き隠るべき心ざまなどはなければ、「かれがれにとだえ置かむ折こそは、さやうに思ひ変ることもあらめ、心ながらも、すこし移ろふことあらむこそあはれなるべけれ」とさへ、思しけり。 八月十五夜、隈なき月影、隙多かる板屋、残りなく漏り来て、見慣らひたまはぬ住まひのさまも珍しきに、暁近くなりにけるなるべし、隣の家々、あやしき賤の男の声々、目覚まして、 「あはれ、いと寒しや」 「今年こそ、なりはひにも頼むところすくなく、田舎の通ひも思ひかけねば、いと心細けれ。 北殿こそ、聞きたまふや」 など、言ひ交はすも聞こゆ。 いとあはれなるおのがじしの営みに起き出でて、そそめき騒ぐもほどなきを、女いと恥づかしく思ひたり。 艶だち気色ばまむ人は、消えも入りぬべき住まひのさまなめりかし。 されど、のどかに、つらきも憂きもかたはらいたきことも、思ひ入れたるさまならで、我がもてなしありさまは、いとあてはかにこめかしくて、またなくらうがはしき隣の用意なさを、いかなる事とも聞き知りたるさまならねば、なかなか、恥ぢかかやかむよりは、罪許されてぞ見えける。 ごほごほと鳴る神よりもおどろおどろしく、踏み轟かす唐臼の音も枕上とおぼゆる。 「あな、耳かしかまし」と、これにぞ思さるる。 何の響きとも聞き入れたまはず、いとあやしうめざましき音なひとのみ聞きたまふ。 くだくだしきことのみ多かり。 白妙の衣うつ砧の音も、かすかにこなたかなた聞きわたされ、空飛ぶ雁の声、取り集めて、忍びがたきこと多かり。 端近き御座所なりければ、遣戸を引き開けて、もろともに見出だしたまふ。 ほどなき庭に、されたる呉竹、前栽の露は、なほかかる所も同じごときらめきたり。 虫の声々乱りがはしく、壁のなかの蟋蟀だに間遠に聞き慣らひたまへる御耳に、さし当てたるやうに鳴き乱るるを、なかなかさまかへて思さるるも、御心ざし一つの浅からぬに、よろづの罪許さるるなめりかし。 白き袷、薄色のなよよかなるを重ねて、はなやかならぬ姿、いとらうたげにあえかなる心地して、そこと取り立ててすぐれたることもなけれど、細やかにたをたをとして、ものうち言ひたるけはひ、「あな、心苦し」と、ただいとらうたく見ゆ。 心ばみたる方をすこし添へたらば、と見たまひながら、なほうちとけて見まほしく思さるれば、 「いざ、ただこのわたり近き所に、心安くて明かさむ。 かくてのみは、いと苦しかりけり」とのたまへば、 「いかでか。 にはかならむ」 と、いとおいらかに言ひてゐたり。 この世のみならぬ契りなどまで頼めたまふに、うちとくる心ばへなど、あやしくやう変はりて、世馴れたる人ともおぼえねば、人の思はむ所もえ憚りたまはで、右近を召し出でて、随身を召させたまひて、御車引き入れさせたまふ。 このある人びとも、かかる御心ざしのおろかならぬを見知れば、おぼめかしながら、頼みかけきこえたり。 明け方も近うなりにけり。 鶏の声などは聞こえで、御嶽精進にやあらむ、ただ翁びたる声にぬかづくぞ聞こゆる。 起ち居のけはひ、堪へがたげに行ふ。 いとあはれに、「朝の露に異ならぬ世を、何を貧る身の祈りにか」と、聞きたまふ。 「南無当来導師」とぞ拝むなる。 「かれ、聞きたまへ。 この世とのみは思はざりけり」と、あはれがりたまひて、 「優婆塞が行ふ道をしるべにて 来む世も深き契り違ふな」 長生殿の古き例はゆゆしくて、翼を交さむとは引きかへて、弥勒の世をかねたまふ。 行く先の御頼め、いとこちたし。 「前の世の契り知らるる身の憂さに 行く末かねて頼みがたさよ」 かやうの筋なども、さるは、心もとなかめり。 いさよふ月に、ゆくりなくあくがれむことを、女は思ひやすらひ、とかくのたまふほど、にはかに雲隠れて、明け行く空いとをかし。 はしたなきほどにならぬ先にと、例の急ぎ出でたまひて、軽らかにうち乗せたまへれば、右近ぞ乗りぬる。 そのわたり近きなにがしの院におはしまし着きて、預り召し出づるほど、荒れたる門の忍ぶ草茂りて見上げられたる、たとしへなく木暗し。 霧も深く、露けきに、簾をさへ上げたまへれば、御袖もいたく濡れにけり。 「まだかやうなることを慣らはざりつるを、心尽くしなることにもありけるかな。 いにしへもかくやは人の惑ひけむ 我がまだ知らぬしののめの道 慣らひたまへりや」 とのたまふ。 女、恥ぢらひて、 「山の端の心も知らで行く月は うはの空にて影や絶えなむ 心細く」 とて、もの恐ろしうすごげに思ひたれば、「かのさし集ひたる住まひの慣らひならむ」と、をかしく思す。 御車入れさせて、西の対に御座などよそふほど、高欄に御車ひきかけて立ちたまへり。 右近、艶なる心地して、来し方のことなども、人知れず思ひ出でけり。 預りいみじく経営しありく気色に、この御ありさま知りはてぬ。 ほのぼのと物見ゆるほどに、下りたまひぬめり。 かりそめなれど、清げにしつらひたり。 「御供に人もさぶらはざりけり。 不便なるわざかな」とて、むつましき下家司にて、殿にも仕うまつる者なりければ、参りよりて、「さるべき人召すべきにや」など、申さすれど、 「ことさらに人来まじき隠れ家求めたるなり。 さらに心よりほかに漏らすな」と口がためさせたまふ。 御粥など急ぎ参らせたれど、取り次ぐ御まかなひうち合はず。 まだ知らぬことなる御旅寝に、「息長川」と契りたまふことよりほかのことなし。 日たくるほどに起きたまひて、格子手づから上げたまふ。 いといたく荒れて、人目もなくはるばると見渡されて、木立いとうとましくものふりたり。 け近き草木などは、ことに見所なく、みな秋の野らにて、池も水草に埋もれたれば、いとけうとげになりにける所かな。 別納の方にぞ、曹司などして、人住むべかめれど、こなたは離れたり。 「けうとくもなりにける所かな。 さりとも、鬼なども我をば見許してむ」とのたまふ。 顔はなほ隠したまへれど、女のいとつらしと思へれば、「げに、かばかりにて隔てあらむも、ことのさまに違ひたり」と思して、 「夕露に紐とく花は玉鉾の たよりに見えし縁にこそありけれ 露の光やいかに」 とのたまへば、後目に見おこせて、 「光ありと見し夕顔のうは露は たそかれ時のそら目なりけり」 とほのかに言ふ。 をかしと思しなす。 げに、うちとけたまへるさま、世になく、所から、まいてゆゆしきまで見えたまふ。 「尽きせず隔てたまへるつらさに、あらはさじと思ひつるものを。 今だに名のりしたまへ。 いとむくつけし」 とのたまへど、「海人の子なれば」とて、さすがにうちとけぬさま、いとあいだれたり。 「よし、これも我からなめり」と、怨みかつは語らひ、暮らしたまふ。 惟光、尋ねきこえて、御くだものなど参らす。 右近が言はむこと、さすがにいとほしければ、近くもえさぶらひ寄らず。 「かくまでたどり歩きたまふ、をかしう、さもありぬべきありさまにこそは」と推し量るにも、「我がいとよく思ひ寄りぬべかりしことを、譲りきこえて、心ひろさよ」など、めざましう思ひをる。 たとしへなく静かなる夕べの空を眺めたまひて、奥の方は暗うものむつかしと、女は思ひたれば、端の簾を上げて、添ひ臥したまへり。 夕映えを見交はして、女も、かかるありさまを、思ひのほかにあやしき心地はしながら、よろづの嘆き忘れて、すこしうちとけゆく気色、いとらうたし。 つと御かたはらに添ひ暮らして、物をいと恐ろしと思ひたるさま、若う心苦し。 格子とく下ろしたまひて、大殿油参らせて、「名残りなくなりにたる御ありさまにて、なほ心のうちの隔て残したまへるなむつらき」と、恨みたまふ。 「内裏に、いかに求めさせたまふらむを、いづこに尋ぬらむ」と、思しやりて、かつは、「あやしの心や。 六条わたりにも、いかに思ひ乱れたまふらむ。 恨みられむに、苦しう、ことわりなり」と、いとほしき筋は、まづ思ひきこえたまふ。 何心もなきさしむかひを、あはれと思すままに、「あまり心深く、見る人も苦しき御ありさまを、すこし取り捨てばや」と、思ひ比べられたまひける。 宵過ぐるほど、すこし寝入りたまへるに、御枕上に、いとをかしげなる女ゐて、 「己がいとめでたしと見たてまつるをば、尋ね思ほさで、かく、ことなることなき人を率ておはして、時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ」 とて、この御かたはらの人をかき起こさむとす、と見たまふ。 物に襲はるる心地して、おどろきたまへれば、火も消えにけり。 うたて思さるれば、太刀を引き抜きて、うち置きたまひて、右近を起こしたまふ。 これも恐ろしと思ひたるさまにて、参り寄れり。 「渡殿なる宿直人起こして、『紙燭さして参れ』と言へ」とのたまへば、 「いかでかまからむ。 暗うて」と言へば、 「あな、若々し」と、うち笑ひたまひて、手をたたきたまへば、山彦の答ふる声、いとうとまし。 人え聞きつけで参らぬに、この女君、いみじくわななきまどひて、いかさまにせむと思へり。 汗もしとどになりて、我かの気色なり。 「物怖ぢをなむわりなくせさせたまふ本性にて、いかに思さるるにか」と、右近も聞こゆ。 「いとか弱くて、昼も空をのみ見つるものを、いとほし」と思して、 「我、人を起こさむ。 手たたけば、山彦の答ふる、いとうるさし。 ここに、しばし、近く」 とて、右近を引き寄せたまひて、西の妻戸に出でて、戸を押し開けたまへれば、渡殿の火も消えにけり。 風すこしうち吹きたるに、人は少なくて、さぶらふ限りみな寝たり。 この院の預りの子、むつましく使ひたまふ若き男、また上童一人、例の随身ばかりぞありける。 召せば、御答へして起きたれば、 「紙燭さして参れ。 『随身も、弦打して、絶えず声づくれ』と仰せよ。 人離れたる所に、心とけて寝ぬるものか。 惟光朝臣の来たりつらむは」と、問はせたまへば、 「さぶらひつれど、仰せ言もなし。 暁に御迎へに参るべきよし申してなむ、まかではべりぬる」と聞こゆ。 この、かう申す者は、滝口なりければ、弓弦いとつきづきしくうち鳴らして、「火あやふし」と言ふ言ふ、預りが曹司の方に去ぬなり。 内裏を思しやりて、「名対面は過ぎぬらむ、滝口の宿直奏し、今こそ」と、推し量りたまふは、まだ、いたう更けぬにこそは。 帰り入りて、探りたまへば、女君はさながら臥して、右近はかたはらにうつぶし臥したり。 「こはなぞ。 あな、もの狂ほしの物怖ぢや。 荒れたる所は、狐などやうのものの、人を脅やかさむとて、け恐ろしう思はするならむ。 まろあれば、さやうのものには脅されじ」とて、引き起こしたまふ。 「いとうたて、乱り心地の悪しうはべれば、うつぶし臥してはべるや。 御前にこそわりなく思さるらめ」と言へば、 「そよ。 などかうは」とて、かい探りたまふに、息もせず。 引き動かしたまへど、なよなよとして、我にもあらぬさまなれば、「いといたく若びたる人にて、物にけどられぬるなめり」と、せむかたなき心地したまふ。 紙燭持て参れり。 右近も動くべきさまにもあらねば、近き御几帳を引き寄せて、 「なほ持て参れ」 とのたまふ。 例ならぬことにて、御前近くもえ参らぬ、つつましさに、長押にもえ上らず。 「なほ持て来や、所に従ひてこそ」 とて、召し寄せて見たまへば、ただこの枕上に、夢に見えつる容貌したる女、面影に見えて、ふと消え失せぬ。 「昔の物語などにこそ、かかることは聞け」と、いとめづらかにむくつけけれど、まづ、「この人いかになりぬるぞ」と思ほす心騒ぎに、身の上も知られたまはず、添ひ臥して、「やや」と、おどろかしたまへど、ただ冷えに冷え入りて、息は疾く絶え果てにけり。 言はむかたなし。 頼もしく、いかにと言ひ触れたまふべき人もなし。 法師などをこそは、かかる方の頼もしきものには思すべけれど。 さこそ強がりたまへど、若き御心にて、いふかひなくなりぬるを見たまふに、やるかたなくて、つと抱きて、 「あが君、生き出でたまへ。 いといみじき目な見せたまひそ」 とのたまへど、冷え入りにたれば、けはひものうとくなりゆく。 右近は、ただ「あな、むつかし」と思ひける心地みな冷めて、泣き惑ふさまいといみじ。 南殿の鬼の、なにがしの大臣脅やかしけるたとひを思し出でて、心強く、 「さりとも、いたづらになり果てたまはじ。 夜の声はおどろおどろし。 あなかま」 と諌めたまひて、いとあわたたしきに、あきれたる心地したまふ。 この男を召して、 「ここに、いとあやしう、物に襲はれたる人のなやましげなるを、ただ今、惟光朝臣の宿る所にまかりて、急ぎ参るべきよし言へ、と仰せよ。 なにがし阿闍梨、そこにものするほどならば、ここに来べきよし、忍びて言へ。 かの尼君などの聞かむに、おどろおどろしく言ふな。 かかる歩き許さぬ人なり」 など、物のたまふやうなれど、胸塞がりて、この人を空しくしなしてむことのいみじく思さるるに添へて、大方のむくむくしさ、たとへむ方なし。 夜中も過ぎにけむかし、風のやや荒々しう吹きたるは。 まして、松の響き、木深く聞こえて、気色ある鳥のから声に鳴きたるも、「梟」はこれにやとおぼゆ。 うち思ひめぐらすに、こなたかなた、けどほく疎ましきに、人声はせず、「などて、かくはかなき宿りは取りつるぞ」と、悔しさもやらむ方なし。 右近は、物もおぼえず、君につと添ひたてまつりて、わななき死ぬべし。 「また、これもいかならむ」と、心そらにて捉へたまへり。 我一人さかしき人にて、思しやる方ぞなきや。 火はほのかにまたたきて、母屋の際に立てたる屏風の上、ここかしこの隈々しくおぼえたまふに、物の足音、ひしひしと踏み鳴らしつつ、後ろより寄り来る心地す。 「惟光、とく参らなむ」と思す。 ありか定めぬ者にて、ここかしこ尋ねけるほどに、夜の明くるほどの久しさは、千夜を過ぐさむ心地したまふ。 からうして、鶏の声はるかに聞こゆるに、「命をかけて、何の契りに、かかる目を見るらむ。 我が心ながら、かかる筋に、おほけなくあるまじき心の報いに、かく、来し方行く先の例となりぬべきことはあるなめり。 忍ぶとも、世にあること隠れなくて、内裏に聞こし召さむをはじめて、人の思ひ言はむこと、よからぬ童べの口ずさびになるべきなめり。 ありありて、をこがましき名をとるべきかな」と、思しめぐらす。 からうして、惟光朝臣参れり。 夜中、暁といはず、御心に従へる者の、今宵しもさぶらはで、召しにさへおこたりつるを、憎しと思すものから、召し入れて、のたまひ出でむことのあへなきに、ふとも物言はれたまはず。 右近、大夫のけはひ聞くに、初めよりのこと、うち思ひ出でられて泣くを、君もえ堪へたまはで、我一人さかしがり抱き持たまへりけるに、この人に息をのべたまひてぞ、悲しきことも思されける、とばかり、いといたく、えもとどめず泣きたまふ。 ややためらひて、「ここに、いとあやしきことのあるを、あさましと言ふにもあまりてなむある。 かかるとみの事には、誦経などをこそはすなれとて、その事どももせさせむ。 願なども立てさせむとて、阿闍梨ものせよ、と言ひつるは」とのたまふに、 「昨日、山へまかり上りにけり。 まづ、いとめづらかなることにもはべるかな。 かねて、例ならず御心地ものせさせたまふことやはべりつらむ」 「さることもなかりつ」とて、泣きたまふさま、いとをかしげにらうたく、見たてまつる人もいと悲しくて、おのれもよよと泣きぬ。 さいへど、年うちねび、世の中のとあることと、しほじみぬる人こそ、もののをりふしは頼もしかりけれ、いづれもいづれも若きどちにて、言はむ方もなけれど、 「この院守などに聞かせむことは、いと便なかるべし。 この人一人こそ睦しくもあらめ、おのづから物言ひ漏らしつべき眷属も立ちまじりたらむ。 まづ、この院を出でおはしましね」と言ふ。 「さて、これより人少ななる所はいかでかあらむ」とのたまふ。 「げに、さぞはべらむ。 かの故里は、女房などの、悲しびに堪へず、泣き惑ひはべらむに、隣しげく、とがむる里人多くはべらむに、おのづから聞こえはべらむを、山寺こそ、なほかやうのこと、おのづから行きまじり、物紛るることはべらめ」と、思ひまはして、「昔、見たまへし女房の、尼にてはべる東山の辺に、移したてまつらむ。 惟光が父の朝臣の乳母にはべりし者の、みづはぐみて住みはべるなり。 辺りは、人しげきやうにはべれど、いとかごかにはべり」 と聞こえて、明けはなるるほどの紛れに、御車寄す。 この人をえ抱きたまふまじければ、上蓆におしくくみて、惟光乗せたてまつる。 いとささやかにて、疎ましげもなく、らうたげなり。 したたかにしもえせねば、髪はこぼれ出でたるも、目くれ惑ひて、あさましう悲し、と思せば、なり果てむさまを見むと思せど、 「はや、御馬にて、二条院へおはしまさむ。 人騒がしくなりはべらぬほどに」 とて、右近を添へて乗すれば、徒歩より、君に馬はたてまつりて、くくり引き上げなどして、かつは、いとあやしく、おぼえぬ送りなれど、御気色のいみじきを見たてまつれば、身を捨てて行くに、君は物もおぼえたまはず、我かのさまにて、おはし着きたり。 人びと、「いづこより、おはしますにか。 なやましげに見えさせたまふ」など言へど、御帳の内に入りたまひて、胸をおさへて思ふに、いといみじければ、「などて、乗り添ひて行かざりつらむ。 生き返りたらむ時、いかなる心地せむ。 見捨てて行きあかれにけりと、つらくや思はむ」と、心惑ひのなかにも、思ほすに、御胸せきあぐる心地したまふ。 御頭も痛く、身も熱き心地して、いと苦しく、惑はれたまへば、「かくはかなくて、我もいたづらになりぬるなめり」と思す。 日高くなれど、起き上がりたまはねば、人びとあやしがりて、御粥などそそのかしきこゆれど、苦しくて、いと心細く思さるるに、内裏より御使あり。 昨日、え尋ね出でたてまつらざりしより、おぼつかながらせたまふ。 大殿の君達参りたまへど、頭中将ばかりを、「立ちながら、こなたに入りたまへ」とのたまひて、御簾の内ながらのたまふ。 「乳母にてはべる者の、この五月のころほひより、重くわづらひはべりしが、頭剃り忌むこと受けなどして、そのしるしにや、よみがへりたりしを、このごろ、またおこりて、弱くなむなりにたる、『今一度、とぶらひ見よ』と申したりしかば、いときなきよりなづさひし者の、今はのきざみに、つらしとや思はむ、と思うたまへてまかれりしに、その家なりける下人の、病しけるが、にはかに出であへで亡くなりにけるを、怖ぢ憚りて、日を暮らしてなむ取り出ではべりけるを、聞きつけはべりしかば、神事なるころ、いと不便なること、と思うたまへかしこまりて、え参らぬなり。 この暁より、しはぶき病みにやはべらむ、頭いと痛くて苦しくはべれば、いと無礼にて聞こゆること」 などのたまふ。 中将、 「さらば、さるよしをこそ奏しはべらめ。 昨夜も、御遊びに、かしこく求めたてまつらせたまひて、御気色悪しくはべりき」と聞こえたまひて、立ち返り、「いかなる行き触れにかからせたまふぞや。 述べやらせたまふことこそ、まことと思うたまへられね」 と言ふに、胸つぶれたまひて、 「かく、こまかにはあらで、ただ、おぼえぬ穢らひに触れたるよしを、奏したまへ。 いとこそたいだいしくはべれ」 と、つれなくのたまへど、心のうちには、言ふかひなく悲しきことを思すに、御心地も悩ましければ、人に目も見合せたまはず。 蔵人弁を召し寄せて、まめやかにかかるよしを奏せさせたまふ。 大殿などにも、かかることありて、え参らぬ御消息など聞こえたまふ。 日暮れて、惟光参れり。 かかる穢らひありとのたまひて、参る人びとも、皆立ちながらまかづれば、人しげからず。 召し寄せて、 「いかにぞ。 今はと見果てつや」 とのたまふままに、袖を御顔に押しあてて泣きたまふ。 惟光も泣く泣く、 「今は限りにこそはものしたまふめれ。 長々と籠もりはべらむも便なきを、明日なむ、日よろしくはべれば、とかくの事、いと尊き老僧の、あひ知りてはべるに、言ひ語らひつけはべりぬる」と聞こゆ。 「添ひたりつる女はいかに」とのたまへば、 「それなむ、また、え生くまじくはべるめる。 我も後れじと惑ひはべりて、今朝は谷に落ち入りぬとなむ見たまへつる。 『かの故里人に告げやらむ』と申せど、『しばし、思ひしづめよ、と。 ことのさま思ひめぐらして』となむ、こしらへおきはべりつる」 と、語りきこゆるままに、いといみじと思して、 「我も、いと心地悩ましく、いかなるべきにかとなむおぼゆる」とのたまふ。 「何か、さらに思ほしものせさせたまふ。 さるべきにこそ、よろづのことはべらめ。 人にも漏らさじと思うたまふれば、惟光おり立ちて、よろづはものしはべる」など申す。 「さかし。 さ皆思ひなせど、浮かびたる心のすさびに、人をいたづらになしつるかごと負ひぬべきが、いとからきなり。 少将の命婦などにも聞かすな。 尼君ましてかやうのことなど、諌めらるるを、心恥づかしくなむおぼゆべき」と、口かためたまふ。 「さらぬ法師ばらなどにも、皆、言ひなすさま異にはべる」 と聞こゆるにぞ、かかりたまへる。 ほの聞く女房など、「あやしく、何ごとならむ、穢らひのよしのたまひて、内裏にも参りたまはず、また、かくささめき嘆きたまふ」と、ほのぼのあやしがる。 「さらに事なくしなせ」と、そのほどの作法のたまへど、 「何か、ことことしくすべきにもはべらず」 とて立つが、いと悲しく思さるれば、 「便なしと思ふべけれど、今一度、かの亡骸を見ざらむが、いといぶせかるべきを、馬にてものせむ」 とのたまふを、いとたいだいしきこととは思へど、 「さ思されむは、いかがせむ。 はや、おはしまして、夜更けぬ先に帰らせおはしませ」 と申せば、このごろの御やつれにまうけたまへる、狩の御装束着替へなどして出でたまふ。 御心地かきくらし、いみじく堪へがたければ、かくあやしき道に出で立ちても、危かりし物懲りに、いかにせむと思しわづらへど、なほ悲しさのやる方なく、「ただ今の骸を見では、またいつの世にかありし容貌をも見む」と、思し念じて、例の大夫、随身を具して出でたまふ。 道遠くおぼゆ。 十七日の月さし出でて、河原のほど、御前駆の火もほのかなるに、鳥辺野の方など見やりたるほどなど、ものむつかしきも、何ともおぼえたまはず、かき乱る心地したまひて、おはし着きぬ。 辺りさへすごきに、板屋のかたはらに堂建てて行へる尼の住まひ、いとあはれなり。 御燈明の影、ほのかに透きて見ゆ。 その屋には、女一人泣く声のみして、外の方に、法師ばら二、三人物語しつつ、わざとの声立てぬ念仏ぞする。 寺々の初夜も、みな行ひ果てて、いとしめやかなり。 清水の方ぞ、光多く見え、人のけはひもしげかりける。 この尼君の子なる大徳の声尊くて、経うち読みたるに、涙の残りなく思さる。 入りたまへれば、火取り背けて、右近は屏風隔てて臥したり。 いかにわびしからむと、見たまふ。 恐ろしきけもおぼえず、いとらうたげなるさまして、まだいささか変りたるところなし。 手をとらへて、 「我に、今一度、声をだに聞かせたまへ。 いかなる昔の契りにかありけむ、しばしのほどに、心を尽くしてあはれに思ほえしを、うち捨てて、惑はしたまふが、いみじきこと」 と、声も惜しまず、泣きたまふこと、限りなし。 大徳たちも、誰とは知らぬに、あやしと思ひて、皆、涙落としけり。 右近を、「いざ、二条へ」とのたまへど、 「年ごろ、幼くはべりしより、片時たち離れたてまつらず、馴れきこえつる人に、にはかに別れたてまつりて、いづこにか帰りはべらむ。 いかになりたまひにきとか、人にも言ひはべらむ。 悲しきことをばさるものにて、人に言ひ騒がれはべらむが、いみじきこと」と言ひて、泣き惑ひて、「煙にたぐひて、慕ひ参りなむ」と言ふ。 「道理なれど、さなむ世の中はある。 別れと言ふもの、悲しからぬはなし。 とあるもかかるも、同じ命の限りあるものになむある。 思ひ慰めて、我を頼め」と、のたまひこしらへて、「かく言ふ我が身こそは、生きとまるまじき心地すれ」 とのたまふも、頼もしげなしや。 惟光、「夜は、明け方になりはべりぬらむ。 はや帰らせたまひなむ」 と聞こゆれば、返りみのみせられて、胸もつと塞がりて出でたまふ。 道いと露けきに、いとどしき朝霧に、いづこともなく惑ふ心地したまふ。 ありしながらうち臥したりつるさま、うち交はしたまへりしが、我が御紅の御衣の着られたりつるなど、いかなりけむ契りにかと道すがら思さる。 御馬にも、はかばかしく乗りたまふまじき御さまなれば、また、惟光添ひ助けておはしまさするに、堤のほどにて、御馬よりすべり下りて、いみじく御心地惑ひければ、 「かかる道の空にて、はふれぬべきにやあらむ。 さらに、え行き着くまじき心地なむする」 とのたまふに、惟光心地惑ひて、「我がはかばかしくは、さのたまふとも、かかる道に率て出でたてまつるべきかは」と思ふに、いと心あわたたしければ、川の水に手を洗ひて、清水の観音を念じたてまつりても、すべなく思ひ惑ふ。 君も、しひて御心を起こして、心のうちに仏を念じたまひて、また、とかく助けられたまひてなむ、二条院へ帰りたまひける。 あやしう夜深き御歩きを、人びと、「見苦しきわざかな。 このごろ、例よりも静心なき御忍び歩きの、しきるなかにも、昨日の御気色の、いと悩ましう思したりしに。 いかでかく、たどり歩きたまふらむ」と、嘆きあへり。 まことに、臥したまひぬるままに、いといたく苦しがりたまひて、二、三日になりぬるに、むげに弱るやうにしたまふ。 内裏にも、聞こしめし、嘆くこと限りなし。 御祈り、方々に隙なくののしる。 祭、祓、修法など、言ひ尽くすべくもあらず。 世にたぐひなくゆゆしき御ありさまなれば、世に長くおはしますまじきにやと、天の下の人の騷ぎなり。 苦しき御心地にも、かの右近を召し寄せて、局など近くたまひて、さぶらはせたまふ。 惟光、心地も騒ぎ惑へど、思ひのどめて、この人のたづきなしと思ひたるを、もてなし助けつつさぶらはす。 君は、いささか隙ありて思さるる時は、召し出でて使ひなどすれば、ほどなく交じらひつきたり。 服、いと黒くして、容貌などよからねど、かたはに見苦しからぬ若人なり。 「あやしう短かかりける御契りにひかされて、我も世にえあるまじきなめり。 年ごろの頼み失ひて、心細く思ふらむ慰めにも、もしながらへば、よろづに育まむとこそ思ひしか、ほどなくまたたち添ひぬべきが、口惜しくもあるべきかな」 と、忍びやかにのたまひて、弱げに泣きたまへば、言ふかひなきことをばおきて、「いみじく惜し」と思ひきこゆ。 殿のうちの人、足を空にて思ひ惑ふ。 内裏より、御使、雨の脚よりもけにしげし。 思し嘆きおはしますを聞きたまふに、いとかたじけなくて、せめて強く思しなる。 大殿も経営したまひて、大臣、日々に渡りたまひつつ、さまざまのことをせさせたまふ、しるしにや、二十余日、いと重くわづらひたまひつれど、ことなる名残のこらず、おこたるさまに見えたまふ。 穢らひ忌みたまひしも、一つに満ちぬる夜なれば、おぼつかながらせたまふ御心、わりなくて、内裏の御宿直所に参りたまひなどす。 大殿、我が御車にて迎へたてまつりたまひて、御物忌なにやと、むつかしう慎ませたてまつりたまふ。 我にもあらず、あらぬ世によみがへりたるやうに、しばしはおぼえたまふ。 九月二十日のほどにぞ、おこたり果てたまひて、いといたく面痩せたまへれど、なかなか、いみじくなまめかしくて、ながめがちに、ねをのみ泣きたまふ。 見たてまつりとがむる人もありて、「御物の怪なめり」など言ふもあり。 右近を召し出でて、のどやかなる夕暮に、物語などしたまひて、 「なほ、いとなむあやしき。 などてその人と知られじとは、隠いたまへりしぞ。 まことに海人の子なりとも、さばかりに思ふを知らで、隔てたまひしかばなむ、つらかりし」とのたまへば、 「などてか、深く隠しきこえたまふことははべらむ。 いつのほどにてかは、何ならぬ御名のりを聞こえたまはむ。 初めより、あやしうおぼえぬさまなりし御ことなれば、『現ともおぼえずなむある』とのたまひて、『御名隠しも、さばかりにこそは』と聞こえたまひながら、『なほざりにこそ紛らはしたまふらめ』となむ、憂きことに思したりし」と聞こゆれば、 「あいなかりける心比べどもかな。 我は、しか隔つる心もなかりき。 ただ、かやうに人に許されぬ振る舞ひをなむ、まだ慣らはぬことなる。 内裏に諌めのたまはするをはじめ、つつむこと多かる身にて、はかなく人にたはぶれごとを言ふも、所狭う、取りなしうるさき身のありさまになむあるを、はかなかりし夕べより、あやしう心にかかりて、あながちに見たてまつりしも、かかるべき契りこそはものしたまひけめと思ふも、あはれになむ。 またうち返し、つらうおぼゆる。 かう長かるまじきにては、など、さしも心に染みて、あはれとおぼえたまひけむ。 なほ詳しく語れ。 今は、何ごとを隠すべきぞ。 七日七日に仏描かせても、誰が為とか、心のうちにも思はむ」とのたまへば、 「何か、隔てきこえさせはべらむ。 自ら、忍び過ぐしたまひしことを、亡き御うしろに、口さがなくやは、と思うたまふばかりになむ。 親たちは、はや亡せたまひにき。 三位中将となむ聞こえし。 いとらうたきものに思ひきこえたまへりしかど、我が身のほどの心もとなさを思すめりしに、命さへ堪へたまはずなりにしのち、はかなきもののたよりにて、頭中将なむ、まだ少将にものしたまひし時、見初めたてまつらせたまひて、三年ばかりは、志あるさまに通ひたまひしを、去年の秋ごろ、かの右の大殿より、いと恐ろしきことの聞こえ参で来しに、物怖ぢをわりなくしたまひし御心に、せむかたなく思し怖ぢて、西の京に、御乳母住みはべる所になむ、はひ隠れたまへりし。 それもいと見苦しきに、住みわびたまひて、山里に移ろひなむと思したりしを、今年よりは塞がりける方にはべりければ、違ふとて、あやしき所にものしたまひしを、見あらはされたてまつりぬることと、思し嘆くめりし。 世の人に似ず、ものづつみをしたまひて人に物思ふ気色を見えむを、恥づかしきものにしたまひて、つれなくのみもてなして、御覧ぜられたてまつりたまふめりしか」 と、語り出づるに、「さればよ」と、思しあはせて、いよいよあはれまさりぬ。 「幼き人惑はしたりと、中将の愁へしは、さる人や」と問ひたまふ。 「しか。 一昨年の春ぞ、ものしたまへりし。 女にて、いとらうたげになむ」と語る。 「さて、いづこにぞ。 人にさとは知らせで、我に得させよ。 あとはかなく、いみじと思ふ御形見に、いとうれしかるべくなむ」とのたまふ。 「かの中将にも伝ふべけれど、言ふかひなきかこと負ひなむ。 とざまかうざまにつけて、育まむに咎あるまじきを。 そのあらむ乳母などにも、ことざまに言ひなして、ものせよかし」など語らひたまふ。 「さらば、いとうれしくなむはべるべき。 かの西の京にて生ひ出でたまはむは、心苦しくなむ。 はかばかしく扱ふ人なしとて、かしこに」など聞こゆ。 夕暮の静かなるに、空の気色いとあはれに、御前の前栽枯れ枯れに、虫の音も鳴きかれて、紅葉のやうやう色づくほど、絵に描きたるやうにおもしろきを見わたして、心よりほかにをかしき交じらひかなと、かの夕顔の宿りを思ひ出づるも恥づかし。 竹の中に家鳩といふ鳥の、ふつつかに鳴くを聞きたまひて、かのありし院にこの鳥の鳴きしを、いと恐ろしと思ひたりしさまの、面影にらうたく思し出でらるれば、 「年はいくつにかものしたまひし。 あやしく世の人に似ず、あえかに見えたまひしも、かく長かるまじくてなりけり」とのたまふ。 「十九にやなりたまひけむ。 右近は、亡くなりにける御乳母の捨て置きてはべりければ、三位の君のらうたがりたまひて、かの御あたり去らず、生ほしたてたまひしを思ひたまへ出づれば、いかでか世にはべらむずらむ。 いとしも人にと、悔しくなむ。 ものはかなげにものしたまひし人の御心を、頼もしき人にて、年ごろならひはべりけること」と聞こゆ。 「はかなびたるこそは、らうたけれ。 かしこく人になびかぬ、いと心づきなきわざなり。 自らはかばかしくすくよかならぬ心ならひに、女はただやはらかに、とりはづして人に欺かれぬべきが、さすがにものづつみし、見む人の心には従はむなむ、あはれにて、我が心のままにとり直して見むに、なつかしくおぼゆべき」などのたまへば、 「この方の御好みには、もて離れたまはざりけり、と思ひたまふるにも、口惜しくはべるわざかな」とて泣く。 空のうち曇りて、風冷やかなるに、いといたく眺めたまひて、 「見し人の煙を雲と眺むれば 夕べの空もむつましきかな」 と独りごちたまへど、えさし答へも聞こえず。 かやうにて、おはせましかば、と思ふにも、胸塞がりておぼゆ。 耳かしかましかりし砧の音を、思し出づるさへ恋しくて、「正に長き夜」とうち誦じて、臥したまへり。 かの、伊予の家の小君、参る折あれど、ことにありしやうなる言伝てもしたまはねば、憂しと思し果てにけるを、いとほしと思ふに、かくわづらひたまふを聞きて、さすがにうち嘆きけり。 遠く下りなどするを、さすがに心細ければ、思し忘れぬるかと、試みに、 「承り、悩むを、言に出でては、えこそ、 問はぬをもなどかと問はでほどふるに いかばかりかは思ひ乱るる 『益田』はまことになむ」 と聞こえたり。 めづらしきに、これもあはれ忘れたまはず。 「生けるかひなきや、誰が言はましことにか。 空蝉の世は憂きものと知りにしを また言の葉にかかる命よ はかなしや」 と、御手もうちわななかるるに、乱れ書きたまへる、いとどうつくしげなり。 なほ、かのもぬけを忘れたまはぬを、いとほしうもをかしうも思ひけり。 かやうに憎からずは、聞こえ交はせど、け近くとは思ひよらず、さすがに、言ふかひなからずは見えたてまつりてやみなむ、と思ふなりけり。 かの片つ方は、蔵人少将をなむ通はす、と聞きたまふ。 「あやしや。 いかに思ふらむ」と、少将の心のうちもいとほしく、また、かの人の気色もゆかしければ、小君して、「死に返り思ふ心は、知りたまへりや」と言ひ遣はす。 「ほのかにも軒端の荻を結ばずは 露のかことを何にかけまし」 高やかなる荻に付けて、「忍びて」とのたまへれど、「取り過ちて、少将も見つけて、我なりけりと思ひあはせば、さりとも、罪ゆるしてむ」と思ふ、御心おごりぞ、あいなかりける。 少将のなき折に見すれば、心憂しと思へど、かく思し出でたるも、さすがにて、御返り、口ときばかりをかことにて取らす。 「ほのめかす風につけても下荻の 半ばは霜にむすぼほれつつ」 手は悪しげなるを、紛らはしさればみて書いたるさま、品なし。 火影に見し顔、思し出でらる。 「うちとけで向ひゐたる人は、え疎み果つまじきさまもしたりしかな。 何の心ばせありげもなく、さうどき誇りたりしよ」と思し出づるに、憎からず。 なほ「こりずまに、またもあだ名立ちぬべき」御心のすさびなめり。 かの人の四十九日、忍びて比叡の法華堂にて、事そがず、装束よりはじめて、さるべきものども、こまかに、誦経などせさせたまひぬ。 経、仏の飾りまでおろかならず、惟光が兄の阿闍梨、いと尊き人にて、二なうしけり。 御書の師にて、睦しく思す文章博士召して、願文作らせたまふ。 その人となくて、あはれと思ひし人のはかなきさまになりにたるを、阿弥陀仏に譲りきこゆるよし、あはれげに書き出でたまへれば、 「ただかくながら、加ふべきことはべらざめり」と申す。 忍びたまへど、御涙もこぼれて、いみじく思したれば、 「何人ならむ。 その人と聞こえもなくて、かう思し嘆かすばかりなりけむ宿世の高さ」 と言ひけり。 忍びて調ぜさせたまへりける装束の袴を取り寄せさせたまひて、 「泣く泣くも今日は我が結ふ下紐を いづれの世にかとけて見るべき」 「このほどまでは漂ふなるを、いづれの道に定まりて赴くらむ」と思ほしやりつつ、念誦をいとあはれにしたまふ。 頭中将を見たまふにも、あいなく胸騒ぎて、かの撫子の生ひ立つありさま、聞かせまほしけれど、かことに怖ぢて、うち出でたまはず。 かの夕顔の宿りには、いづ方にと思ひ惑へど、そのままにえ尋ねきこえず。 右近だに訪れねば、あやしと思ひ嘆きあへり。 確かならねど、けはひをさばかりにやと、ささめきしかば、惟光をかこちけれど、いとかけ離れ、気色なく言ひなして、なほ同じごと好き歩きければ、いとど夢の心地して、「もし、受領の子どもの好き好きしきが、頭の君に怖ぢきこえて、やがて、率て下りにけるにや」とぞ、思ひ寄りける。 この家主人ぞ、西の京の乳母の女なりける。 三人その子はありて、右近は他人なりければ、「思ひ隔てて、御ありさまを聞かせぬなりけり」と、泣き恋ひけり。 右近はた、かしかましく言ひ騒がむを思ひて、君も今さらに漏らさじと忍びたまへば、若君の上をだにえ聞かず、あさましく行方なくて過ぎゆく。 君は、「夢をだに見ばや」と、思しわたるに、この法事したまひて、またの夜、ほのかに、かのありし院ながら、添ひたりし女のさまも同じやうにて見えければ、「荒れたりし所に住みけむ物の、我に見入れけむたよりに、かくなりぬること」と、思し出づるにもゆゆしくなむ。 伊予介、神無月の朔日ごろに下る。 女房の下らむにとて、たむけ心ことにせさせたまふ。 また、内々にもわざとしたまひて、こまやかにをかしきさまなる櫛、扇多くして、幣などわざとがましくて、かの小袿も遣はす。 「逢ふまでの形見ばかりと見しほどに ひたすら袖の朽ちにけるかな」 こまかなることどもあれど、うるさければ書かず。 御使、帰りにけれど、小君して、小袿の御返りばかりは聞こえさせたり。 「蝉の羽もたちかへてける夏衣 かへすを見てもねは泣かれけり」 「思へど、あやしう人に似ぬ心強さにても、ふり離れぬるかな」と思ひ続けたまふ。 今日ぞ冬立つ日なりけるも、しるく、うちしぐれて、空の気色いとあはれなり。 眺め暮らしたまひて、 「過ぎにしも今日別るるも二道に 行く方知らぬ秋の暮かな」 なほ、かく人知れぬことは苦しかりけりと、思し知りぬらむかし。 かやうのくだくだしきことは、あながちに隠ろへ忍びたまひしもいとほしくて、みな漏らしとどめたるを、「など、帝の御子ならむからに、見む人さへ、かたほならずものほめがちなる」と、作りごとめきてとりなす人ものしたまひければなむ。 あまりもの言ひさがなき罪、さりどころなく。
次の