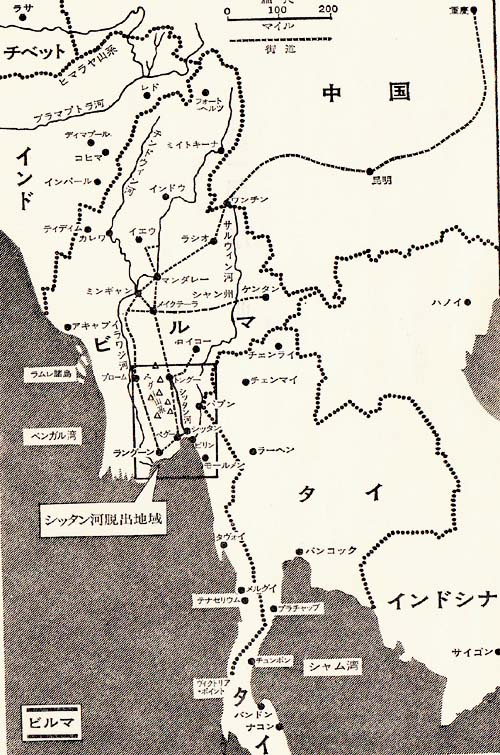7/4発売!!『ベンガル料理はおいしい』の著者石濱匡雄&ユザーンが監修したレトルト商品『ベンガリーマトンカレー』を発売。ご自宅で本格ベンガルカレーをご賞味ください!|合同会社36チャンバーズ・オブ・スパイスのプレスリリース

ベンガルの宗教文化の歴史とその遺産 バングラデシュは、ポッダ川(ガンジス川)やジョムナ川(ブラフマプトラ川)、メグナ川が織りなす肥沃なデルタ地帯の下流域、歴史的にはベンガル地方と呼ばれるインド亜大陸の東部地域に位置する。 本稿では、今日のバングラデシュの社会・文化が形づくられる背景としての、ベンガル地方の宗教文化の歴史を概観する。 人々の間で育まれてきた多様な宗教文化の伝承を、ベンガル地方の地域社会の歴史に位置付けて、現代のバングラデシュに受け継がれる豊かな知的遺産の系譜を見てゆきたい。 1.古代仏教が栄えたベンガル 紀元前6世紀から繁栄するマガダ王国は、今日のインド・ビハール州南部からベンガル地方に展開し、仏教の開祖ゴータマ・ブッダや、ジャイナ教(「勝利者の教え」という意味)の開祖マハーヴィーラが活躍した古代王国として知られる。 やがて、パータリプトラ(現インド・ビハール州都パトナ)を王都とする古代帝国マウリヤ朝(前4-前2世紀)が興り、チャンドラグプタ王(在位、前317-前293年頃)によって、アフガニスタンの東部を含む北西インドからデカン高原まで、インド亜大陸のほぼ全域をカヴァーする古代帝国を打ち立てる。 政治論の古典として名高い『実利論』(アルタシャーストラ)の作者とされるカウティリヤは、チャンドラグプタ王の宰相であった。 チャンドラグプタ王の孫アショーカ王(在位、前268-前232年頃)の時代にマウリヤ朝は、現在のインド・オリッサ地方のカリンガ王国を征服し、最大版図を獲得する。 この戦争で、アショーカ王は殺生の無益さを自覚し、その政治理念を仏教のダルマ(法)に求めて法勅として発布し、各地の摩崖や石柱に刻んだ。 次のグプタ朝(320-550年頃)は、やはりパータリプトラを王都とし、北インド一帯から南インドまでを統一する大帝国を建設する。 官僚制度を整備し、徴税機構を再編し、貨幣経済の発達を促すことで、北インドの諸都市は繁栄する。 歴代の王はヴェーダ祭式を行い、バラモン司祭を重用したが、工芸や建築に優れたグプタ様式は、特にアジャンター・エローラ石窟の仏教美術で知られる。 8世紀中頃から12世紀には、ベンガル地方からビハール州にかけて、パーラ朝が興る。 パーラ朝の王家は仏教に帰依し、ダルマパーラ王(在位、770-810頃)の治世にインド最大の勢力となる。 パーラ朝のもとでタントラ仏教と呼ばれる後期大乗教、あるいは密教が発展し、パーラ朝様式と呼ばれる仏教美術を生み出す。 王家が寄進を行ったナーランダーやヴィクラマシラー(ともに現ビハール州内)、またバングラデシュ領内のパハルプル(ソーマプラ僧院)などの僧院遺跡から、当時の仏教文化の繁栄がうかがえる。 中国の玄奘三蔵(602-664)や義浄(635-715)もこれらの僧院を訪れ、ネパール、チベット、東南アジアからも多様な留学僧が集まり、学芸の交流が深まった。 2.ヒンドゥー教とベンガル 11世紀末から13世紀中頃には、ノボディープ(現インド西ベンガル州ノディア県)を王都とするセーナ朝が興る。 ヒンドゥー教を庇護したセーナ朝は、12世紀半ばにはベンガル全域を版図におさめる。 しかし、第五代ラクシュマナ・セーナ王(ロッコン・シェン、在位1178-1205年頃)の末期に、バクティヤール・キルジーがノボディープに侵攻し、現在のバングラデシュ・ダッカ近郊のビクラムプル(現ムンシゴンジ県)に拠点を移す。 セーナ朝のもとでは、ヴィシュヌ派のサンスクリット宗教詩『ギータ・ゴーヴィンダ』(牛飼いの歌)の作者で知られるジャヤデーヴァが活躍するなど、ヒンドゥー教にちなんだ文学や芸術が発展する。 他方、王権の庇護を失った仏教は徐々に衰退するが、民衆レベルでは仏教の密教化やヒンドゥー教との習合が進み、10~12世紀の密教行者の伝承を集めたベンガル語の宗教詩『チョルジャ・ギティ』が生まれる。 これは、ベンガルの最古の宗教文学としてベンガル語の源流とされるとともに、バングラデシュの無形文化遺産として知られる今日のバウルの歌謡伝承にもその影響を見ることができる。 3.イスラームとベンガル バクティヤール・キルジーの登場で、ベンガルにはイスラーム王権の支配が及び、新たな時代がはじまる。 1576年にベンガルはムガル帝国(16世紀中-1858)の版図に入り、ベンガルに派遣された太守(ナワーブ)のもとで、地方のヒンドゥー勢力は在地領主として統治に組み込まれる。 イスラーム建築や北インド様式の宮廷音楽が発達し、民衆宗教の世界では、土着のヒンドゥー文化と習合したスーフィー聖者への信仰が広まる。 スーフィーはアラビア語の「スーフ」(羊毛)に由来し、元来は粗衣粗食で遍歴する修行者を意味し、イスラーム世界では広くみられる多様な聖者信仰の伝統である。 スーフィー聖者は固有の儀礼体系や思想を通してイスラームの教えを実践し、それを地域社会の人々に広めた。 特に、ベンガル地方でのスーフィー聖者の活躍は、偶像崇拝を否定するイスラームと、多神教的世界のヒンドゥー教という両極の世界を媒介する存在として、人々へのイスラームの布教に大きな役割を果した。 たとえば、仏教とヒンドゥー教に、イスラームのスーフィー思想が習合したバウルの伝承や、現世利益を求める庶民信仰の受け皿として機能してきた各地の聖者廟など、現代バングラデシュの民衆信仰の世界でも、今も様々に見ることができる。 他方、ベンガルのヒンドゥー社会では、バクティ信仰と呼ばれるクリシュナ神への帰依と献身を説くヒンドゥー教ヴィシュヌ派の聖者チャイタニヤ(1486-1533)が活躍する。 賑やかな楽曲とともにクリシュナ神の御名を唱えて行列を組むキールタン(キットン)などの民衆的なヒンドゥー教を実践し、それはインド全域のヒンドゥー社会に広く影響を与えた。 仏教を庇護したパーラ朝や、ヒンドゥー教を庇護したセーナ朝など、ベンガルは歴史的に多様な宗教文化が栄えたが、13世紀に開始されるイスラーム化は、イスラーム王権の成立やスーフィー聖者を媒介とした多様なイスラーム文化を地域社会に浸透させた。 イギリスの植民地統治が本格化する頃には、ヒンドゥー教徒とムスリム(イスラーム教徒)の人口はほぼ拮抗し、特に東ベンガル地方は、英領インドでも最もムスリム人口が集住する地域となっていた。 4.植民地支配とベンガル ムガル帝国時代のベンガルは、インドの肥沃な穀倉地帯と呼ばれ、その富を求めてインド西部のマラータ軍が侵入を繰り返し、17世紀以降はヨーロッパ勢力の進出が顕著になる。 ポルトガル人、オランダ人、フランス人が、ベンガル湾岸沿いの各地に商館を築いて覇を競うが、1757年のプラッシーの戦いや1764年のブクサールの戦いでイギリス東インド会社が勝利し、最終的にイギリス人の覇権が確立する。 やがてベンガルは、英領インドの首都カルカッタ(コルカタ)を擁する植民地統治の要として発展する。 ロンドンに次ぐ、大英帝国の第二の都市となったカルカッタは、政治、経済、芸術・文化の中心地として繁栄し、西洋世界との窓口としてインドの近代化をリードする。 諸宗教の理念を統合して社会改革運動を主導した近代インドの父ラム・モホン・ラエ(1774-1833)や、シカゴ宗教会議でキリスト教文明に比肩するインド文明の精神性の高さを体現したスワーミー・ヴィヴェーカーナンダ(ビベカノンド、1863-1902)、西洋の近代文学とベンガルの宗教文学の伝統を華麗な詩文学に融合させたノーベル賞作家タゴール(1861-1943)、統一インドの独立を夢見て、インパール作戦では日本軍と協力してインド国民軍を指揮したネタジー・スバス・チャンドラ・ボース(シュバシュ・チョンドロ・ボシュ、1897-1945)など、南アジアの近代史に名前をとどめる多彩な人材を輩出する。 5.ベンガルの知的遺産の伝統 しかし、1905年のベンガル分割令とその後のムスリム連盟の創設、宗派別選挙制度の導入などの植民地政府の分割統治策によって、本来はバウルなどの習合文化を通して共生していたヒンドゥー教徒とムスリムは対立を深めるようになり、最終的に、1947年にインドとパキスタンは分離独立を選択する。 ヒンドゥー人口の多い西ベンガル地方はインドの一部として今日のインド西ベンガル州となり、ムスリム人口の多い東ベンガル地方は、東パキスタンとして独立する。 しかし、その後の西パキスタン政府の圧政に対するベンガルの人々の闘いによって、建国の父シェイク・ムジブル・ラフマン(シェイク・ムジブル・ロホマン、1920-1975)のもと、1971年に現在のバングラデシュが誕生する。 このように、ベンガル地方はイギリス植民地支配の様々な矛盾が集約され、独立後もそれに伴う多大な犠牲を背負わされることで、政治的には苦難の道を歩むことになる。 しかし、長い歴史の中で培われてきた豊かな文化伝承を背景として、植民地期のベンガルの人々が残した多様な知的遺産の伝統は、たとえば、ベンガル飢饉の人的要因を解明した厚生経済学でノーベル経済学賞を受賞したアマーティア・セーン(オモルット・シェン、1933-)や、「死を待つ人の家」をコルカタに建てたマザー・テレサ(1910-97)、「貧者の銀行」として知られるグラミン銀行を創設してノーベル平和賞を受賞したムハンマド・ユヌス(1940-)など、東西ベンガル社会の多彩な人々の活躍を通して、今も受け継がれていると言えるだろう。 (文責:外川昌彦).
次の